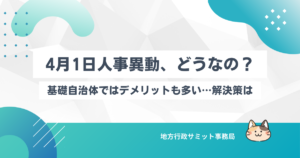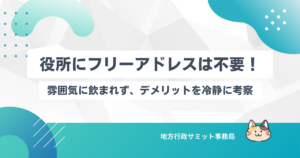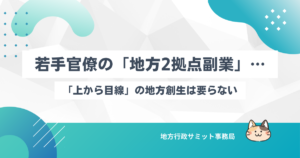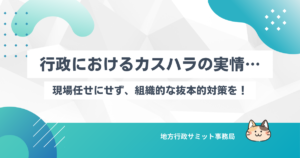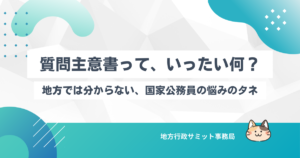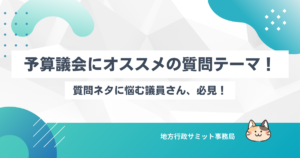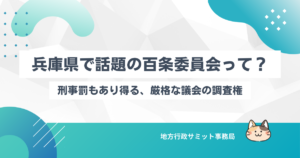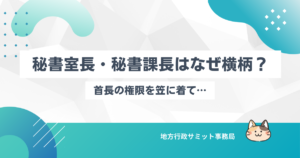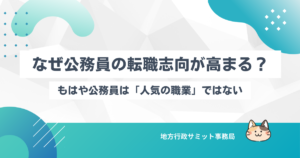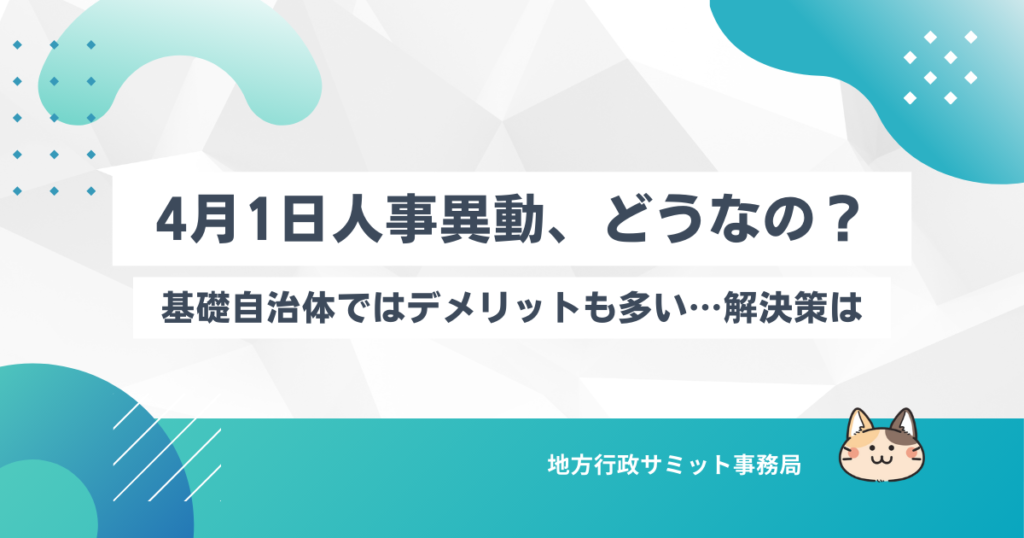
【この記事で分かること】
- 4/1付け人事異動のデメリット
- 4/1付け以外に人事異動を行うメリット・デメリット
- 人事異動のタイミングの理想
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、地方自治体の4月1日付け人事異動というものについて、そのデメリットを考察してみようと思います。
 にゃん子
にゃん子特に基礎自治体では、4月1日は超多忙なので、人事異動をやってる場合じゃないという話があるのにゃ。
自治体の人事異動は4月1日付けが基本
一般に、地方自治体の人事異動は、そのほとんどを4月1日付けで行います。
この背景にある考え方は、いくつかあります。


【理由①】会計年度が4月1日に始まる
地方自治法の条文を持ち出すまでもありませんが、地方自治体の会計年度は、4月1日に始まって、翌年3月31日に終わります。
地方自治法(抄)
(会計年度及びその独立の原則)
第二百八条 普通地方公共団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
そのため、4月1日付けで新たな業務執行体制を構築し、1会計年度の間を、同じ体制で職務遂行ができるようにする、というのは、きわめて合理的で、わかりやすい考え方だと言えるでしょう。
なお、民間企業でも、多くの企業がこの会計年度を採用しています。


【理由②】新規職員の採用が4月1日付け、定年退職は3月31日付け
また、地方自治体の会計年度だけでなく、日本の学校においても、学校年度は4月1日に始まり、3月31日に終わります。
そのため、高校・大学等で学びを終えた新社会人は、3月に学校を卒業し、4月から新たな職場で働くこととなるのが一般的です。
また、職員の定年退職も、3月31日付けとなることが一般的。
そのため、
職員の採用・退職という新陳代謝は、3月31日~4月1日にまとまって起こる
こととなりますので、この人の動きに合わせて人事異動を行うことには、一定の合理性・妥当性があると言えるでしょう。
4月1日付け人事異動のデメリット
ところが、この4月1日付けの人事異動には、デメリットもあります。
【デメリット①】住民窓口は繁忙期である
先ほど書いた「新陳代謝は、3月31日~4月1日にまとまって起こる」というのは、何も役所に限った話ではなく、
日本全国、どのような業界でも同時に起こっている
ことです。
そのため、3月下旬~4月上旬というのは、引っ越しを伴う人生の転機を迎える人が非常に多く、それゆえに住民基本台帳関係事務を行う住民窓口は、人でごった返します。
当然、そのごった返した人の対応をするのは、役所の窓口担当職員なわけですが、この1年で一番忙しい時期に、人事異動で戦力を他部署へ送り出し、そして新人を新たに受け入れるというのは、現場にとっては非常につらいもの。
新人に、新たな仕事を教えることもまた1つの業務負荷になるわけですが、その業務負荷を負いながら、一番の繁忙期を迎えないといけないわけですからね。


【デメリット②】税務事務も年度またぎで業務多忙である
また、
税務事務も、繁忙期を年度またぎで迎える
ことで知られています。
市町村民税であれば、3月15日が期限となる申告書を課税台帳に落とし込み、5~6月の当初課税に向けて、追い込みをかけていく時期。
また、固定資産税も、評価替え以外の年は4月初旬に納税通知書を発送するため、住民からの問い合わせ対応に追われますし、また縦覧への対応にかかる事務も発生します。
こういった事務がピークアウトするのは、市町村民税の第1期納期を終える6月末ごろというのが定番です。


特に最近、地方税まわりの制度改正が激しかったり、システム標準化への対応があったりして、税務部署が疲弊しているという話はよく聞きますね…
昔は税務って、割と人気ある部署だったのですが…最近は激務で不人気部署になっているようです。
「税務に行くくらいなら、財政の方がマシ」という人の話も聞いたよ。
7月1日付け人事異動のメリット・デメリット
一方、たとえば国家公務員を見てみると、通常国会閉会後の7月ごろに、幹部職員を中心とした大規模人事異動を行うなど、必ずしも4月1日付けの人事異動を行っていません。
たとえば、仮に7月1日としたとして、地方自治体において、7月1日付けの人事異動を行うことについて、メリットやデメリットはあるでしょうか。
【メリット①】住民窓口・税務事務をピークアウトさせてから異動できる
先ほど述べたように、3月~4月は住民窓口や税務事務がピークを迎える時期になります。
そのため、たとえば7月1日付け人事異動が行われると、こういった事務のピークに、戦力を維持したまま臨むことができるため、効率的に事務を遂行することができます。
ちなみに、国税の税務署職員は、7月人事異動が基本になっているので、事務のピークを過ぎてから異動できるようなしくみになっているようです。


【メリット②】国との人事交流でタイミングを合わせやすい
また、国では幹部職員を中心にした人事異動が、通常国会閉会後の7月ごろに行われます。
そのため、たとえば国から職員を受け入れている自治体にとっては、自分のところの人事異動も7月に行うことで、国の職員受け入れと一体的な体制整備を行うことが可能になります。



「国の職員受け入れを前提に人事異動の時期を変えるなんて…」
という意見もありそうですが、多くの場合、国の職員は自治体の幹部として受け入れることになるので、その幹部が能力を発揮できるような人事配置を行えることには、実利も大きいと言えるでしょう。


【デメリット①】年度単位で動く事務は引き継ぎが大きくなる
ここまで語ってきた住民窓口や税務事務は、年度をまたいで事務のピークがやってきますが、一方でそれら以外の
多くの施策・事業は、会計年度単位で進行管理することが一般的
です。
特に、新規事業については、議会の議決を得た直後となる4月から業務の遂行に入り、年度末をゴールに設定して取組を進めることが一般的でしょうから、この途中で事務引継ぎが生じるのは、あまり合理的だとは言えません。


【デメリット②】職員の採用・退職とはタイミングがずれる
また、これも先ほど述べたことの裏返しになりますが、3月31日に職員が退職し、4月1日付けで新たな職員が採用されます。
したがって、仮にすべての人事異動を7月1日付けとかにしようとしても、4月1日~6月30日までの間、退職した職員の穴をどのように埋め、新規採用職員をどこに配置するかは検討せざるを得ないのです。



退職した人の後任に新人なんて入れられないからにゃ…
人事異動時期を固定することの問題点
ところで、これら両者のパターンは、そもそも「どこか一定のタイミングで、一斉に人事異動をかける」という前提にたっていますが、これは裏を返すと、
「そのタイミングを逃すと、1年間は異動がないまま過ごさざるを得ない」
ということになります。
この状況にもまた、大きな課題があります。
【問題点①】新たな行政課題に機動的に対応できない
行政課題は、新たな会計年度を待って発生するわけではありません。
たとえば、新型コロナウイルス感染症対策への対応は、令和元年度の1月ごろから頭をもたげてきましたが、4月1日付け人事異動を控えている人事課や部局総務課では、担当レベルは、



「できれば体制整備は4月1日付け人事異動でまとめて行いたいなあ…」
と思っていたことでしょう。
しかし、そんな悠長なことを言っていられないほど、新型コロナ問題は日に日に大きくなり、体制整備がなされない現場の負担感は増す一方でした。
「4月1日付け人事異動以外の選択肢」がもしあれば、4月1日を待つことなく機動的な人事異動で体制整備を行いやすかった
面はあったと言えるでしょう。
これに限らず、「4月1日付け人事異動」をかっちりと固めすぎていると、それ以外の選択肢が「異例」扱いとなり、そのカードを切るのに大きな判断が必要となって、結果として新たな行政課題に対する体制整備が遅れ、初動ミスが生じる…
ということが起こりがちです。


【問題点②】人間関係トラブルへの対応が長期化する
また、人事異動が4月1日付けで固定化すると、人間関係トラブルへの対応が長期化する傾向にもあります。
たとえば、上司と部下の折り合いが悪くて組織内の意思疎通がうまくいかないとか、、職場内で色恋沙汰が生じて業務に支障が出るとか、あるいは課長同士の仲が悪くて組織間・政策間連携がうまくいかないとか…。
こういった
「人事異動がもっとも手っ取り早い解決策」である状況に陥った際、人事異動が年1回に固定化されていると、その4月1日までの間は、そのトラブルを解決できない
状況が続きます。
人事異動が4月1日付け以外にも柔軟に行える環境があれば、人間関係由来のトラブルを早期に解決しやすくなるのですが…。


【提言】4月1日付け異動+αを試行してみては
このように、「4月1日付け人事異動」で人事異動を固定化させてしまうことについては、一定の合理性は認められる一方で、さまざまなデメリットも生じさせます。
そこで、たとえばの提案なのですが、
のはいかがでしょうか。
実際、国家公務員では、退職・採用を含めた4月1日付け人事異動と、通常国会閉会後の幹部人事異動との2本立てで、人事異動を運用しています。
こうすることによって、繁忙期における人事異動のダメージを軽減することができますし、また人事異動が1年間の中に複数回行われることによって、人間関係のトラブルを人事異動で解決する機会を増やすことができます。
人事課や部局総務課の負担は増えますし、所属長的にも人の入れ替わりが増えることによる管理の難しさは生じるかもしれませんが、一考に値するのではないかと個人的には考えています。
霞が関では、それを当然のことのようにルーティン業務にできているわけだしね。
まとめ
以上、本日は、地方自治体において4月1日付け人事異動が基本となっている現状について、そのデメリットを整理しつつ、別の時期に人事異動を行うことについての検討を行ってみました。
ほとんどの自治体で慣行となっている4月1日付け人事異動については、もちろんそれなりの合理性があるのですが、一方でこの時期に繁忙期を迎える部署にとっては大きな負担となります。
また、人事異動の時期が固定化すると、人間関係のトラブルも長期化してしまうという問題もまた生じてしまうので、たとえば年に2回人事異動の時期をもうけるなど、人事異動に伴う弊害を軽減するための取組にも、一考の余地はあると考えます。
人事異動、自治体の運命も左右しますし、同時に職員一人ひとりの運命も左右します。それだけに、少なくとも制度面では、できるだけ多くの人が納得できるような仕組みを構築したいところですね。