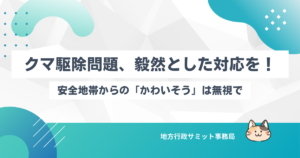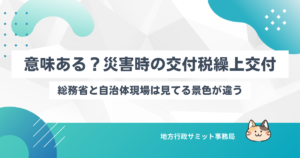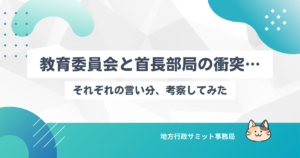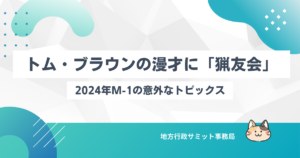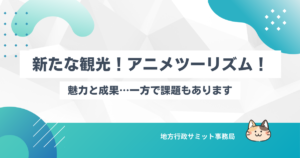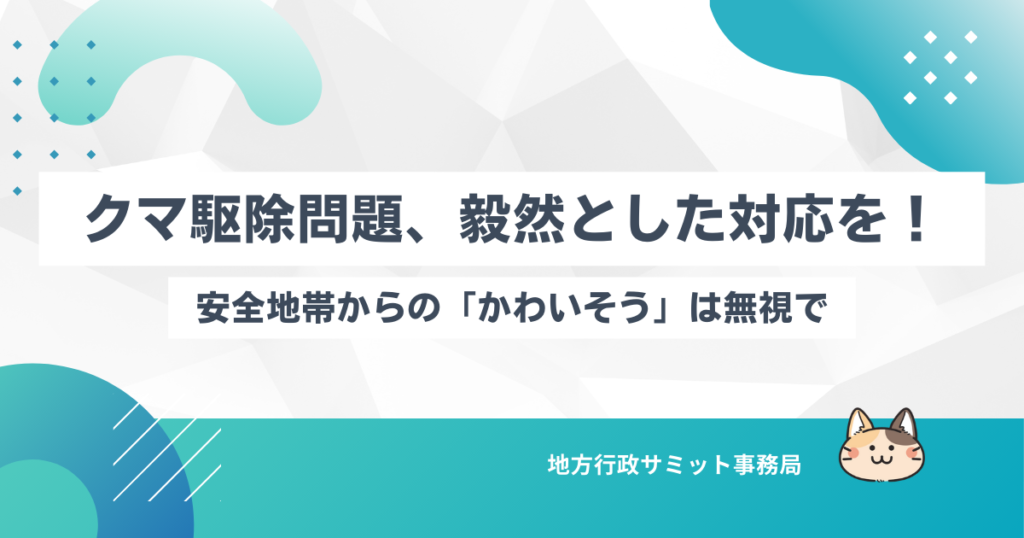
【この記事で分かること】
- 地方自治体におけるクマ問題の現状
- クマ問題に取り組む自治体への苦情電話の状況
- クマ問題への対応としてのジビエ
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、自治体を悩ませるクマ問題について取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子都市部の人には伝わりにくいけど、地方部では本当に深刻な行政課題なのにゃ。
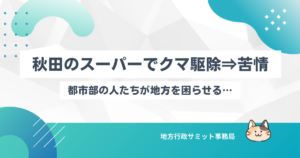
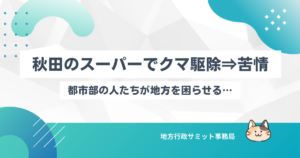
社会問題化する「クマ被害」
2023年(令和5年)は、全国的に、クマによる人身被害が多発した年でした。
基本的には山奥に生息するとされているクマが、今年はエサとなるドングリが不作となった中、高齢化等によって管理されずに放置された果樹園などに降りてきて、その中で住民と遭遇し、事故になってしまう…という事例が非常に多かったです。


特に、市街地周辺にまで降りてきたクマは
と呼ばれ、人を恐れずに作物を荒らしたり生ごみをあさったり、何より学校周辺に表れて子どもたちに危害を加える恐れがあるなど、そのリスクは非常に深刻です。
環境省では、既定予算を活用して今年度のクマ被害対策に向けた事業を行っているほか、令和5年度補正予算を活用した「生息状況の把握⇒冬眠明けのタイミングで駆除」といった取り組みを進めようとしているなど、国レベルでもクマ問題に向けた対策が進められています。
北海道東北地方知事会がクマ対策の緊急要望
とりわけ、クマの生息地を抱える北海道や東北では、その被害は本当に深刻なものとなっています。
そこで、北海道と東北地方の県からなる「北海道東北地方知事会」では、こういったクマ被害を受けて、
をとりまとめ、環境省と農林水産省へ要望活動を行いました。


要望のポイントとしては…
- クマ類を指定管理鳥獣に指定すること
- クマ類の捕獲従事者の確保が難しくなっていることを踏まえた人材育成
- 捕獲強化に向けた事業の実施や出没対策に係る財政・技術的支援
- 「鳥獣被害防止総合対策交付金」の十分な予算確保
- 捕獲器具に係る運用の明確化や法令等の見直し
- クマ類の捕獲従事者が非難を浴びないような、捕獲の必要性の啓発
といった内容になっており、こうした要望活動もあって、現在クマ類については、指定管理鳥獣の指定を受けるに至っています。
クマは駆除するしかない…その理由
クマの駆除については、感情的な面からさまざまな意見があることは一般論としては理解しますが、実際にクマと人とが直面すると、
- クマに襲われて命を落とすリスク
- クマに襲われて大けがをするリスク
- クマが農作物を荒らし、地域住民の経済活動に被害を与えるリスク
- 人を恐れないアーバンベアが市街地に現れると、学校に通う子どもたち含め、被害が著しく増加するリスク
といったように、人々の命や生活にかかわる、重大な問題が発生します。
特に冬眠前の、エサを求めているクマは非常に事故リスクが高いです。
子ども向け絵本に描かれるような「クマさん」「こぐまちゃん」とは、その様相が大きく異なることは、言うまでもありません。
こうしたことから、
特に人の生活圏に現れたクマについては、その地域に暮らす人たちの命と生活を守るために、駆除する以外の選択肢はあり得ない
のです。
問題はクマを駆除する担い手がいない
さて、こういったクマを駆除する役割を担うのは、多くの場合地域の狩猟者であり、その団体である猟友会が重要な役割を果たします。
しかしながら、山奥で狩猟を行う狩猟者は、他の中山間地域の政策課題と同様の話になるのですが、やはり
高齢化が進んでおり、若い担い手がいない
という課題に直面しています。
山奥に入って、クマと対峙する…考えただけで、非常に過酷な仕事になるのですが、そんな過酷な仕事を、現状、ベテランの狩猟者さんたちが担ってくれているのですが、やはり新たな担い手が増えない中、増加するクマに対応しきれないという課題を抱えています。
こうした課題を解決するためには、若い人含め、多くの人が狩猟者になれるようなインセンティブ、仕掛けづくりが必要になってくるわけですが、そういった政策を練るに際してはやはり財源が必要となることも多いため、そういった点を国に要望していると考えられます。
担い手への心無い批判も大問題に
また、担い手確保に際しては、高齢化への対応や新たな担い手発掘だけでなく、「今いる担い手をやめさせない」という取組も、実は非常に重要です。
というのも、北海道・東北地方の自治体には、クマを駆除するたびに



「クマちゃんがかわいそう!」



「なぜそんなひどいことをするんだ!」
などという批判の電話が、役所の担当課に殺到してしまうのです。
自治体への苦情の電話は「クマちゃんを守れ」だけではなく「人里に出たクマを何とかしろ」という、真逆の内容のものも多々含まれます。
後者の方は、住民の命や生活を守るうえで切実な声になりますので、しっかり対応しないといけませんが、前者の方は、クマ被害とは無縁のところから上げられている声であることが多く、自治体にとっては業務妨害以外の何物でもありません。
これにより、ただでさえ
クマ対策で業務量が増加している担当課に、苦情電話への対応という追加的な負荷がかかり、自治体は大きく疲弊
しています。
加えて、こういった心ない批判の声が大きくなると、既存の狩猟者のモチベーションにも影響してしまいますし、新たな担い手が生まれにくくなってしまうという問題も生じます。
クマ問題に悩む自治体にとって、この手の苦情電話は、本当に頭が痛く、悩ましい問題です。
子熊の駆除は特に苦情電話が強くなる…
特に、子熊を駆除したりすると、そういった批判の声はより大きくなってしまいます。
子熊については、小さくて可愛く見えることから、特に駆除したくない気持ちもわかるのですが、
- 子熊の近くには母熊がいることが多く、母熊は特に危険性が高いことから、一斉に駆除する必要がある
- 子熊のうちから人里に出てくるような状態だと、成獣化した後にアーバンベア化する可能性が高い
といったことから、いわゆる「問題個体」となることがほとんどで、
人の命と生活を守るためには、むしろ子熊こそ駆除せざるを得ない
のが実情です。
しかしながら、一部メディアが、そういった「子熊の駆除」を感傷的な表現でネットニュースに流したりすることに伴って、「子熊駆除の必要性」が忘れ去られたまま、苦情電話の呼び水となっている現状があります。



子熊を逃がすというのが、いかに地方部にとって恐ろしく、罪深いことなのか、もっと多くの人に知ってほしいにゃ…
苦情には毅然とした対応&駆除の必要性を積極的に説明を
先ほども申し上げましたように、こういった、クマ駆除に対する苦情については、自治体の立場でみてみると、業務妨害以外の何物でもありません。
ですので、こういった苦情については、
毅然とした態度で、モンスターカスタマーとして取り扱うことが相当
であり、「業務妨害だと伝え、以降の対応を打ち切る」という対応を徹底することが重要です。
「苦情の電話を途中で切る」というのは、電話を実際に手に取る職員にとって、なかなか勇気のいる行動ですので、組織として「クマ駆除に対する苦情はそのように取り扱う」と意思決定し、組織ルールとして各職員に伝えるのが妥当でしょう。
また、職員が安心して苦情対応を行うためには「クマ駆除は必要なことである」という世論が主流になることも大切です。
ですので、たとえば…
- 国が主体となった、クマ駆除の必要性についての啓発
- ACジャパンのCMで、人里に現れるクマの危険性やクマ駆除の必要性をPR
といった啓発の取組を重ねていくことにより、クマ駆除の必要性を、直接的な被害のない都市部も含め、全国レベルで周知していくことが求められています。
北海道東北地方知事会が要望で求める「クマ類の捕獲従事者が非難を浴びないような、捕獲の必要性の啓発」は、まさにこういった現状と課題意識から来ているものだと言えるでしょう。
ACジャパンのクマ駆除CMは、ホントに早くやったらいいのに…と思います。
クマ愛護団体は都市部にある…
さて、こういった、自治体のクマ駆除に批判的な声を上げる「クマ愛護団体」ですが、
こういった団体は、クマ被害に苦しむ山間部の自治体ではなく、都市部に立地している
ことが、大きな問題として指摘されています。


たとえば、こういったクマを守るための取り組みを推進する、一般財団法人日本熊森協会という団体があるのですが、この団体は兵庫県西宮市に拠点を構えています。
兵庫県西宮市は、大阪市と神戸市という、関西の2つの大都市の間に立地する、人口約45万人の中核市。いわゆる「三大都市圏」の一角を占める位置にいる、典型的な都市部の自治体です。
そのような都市部ですので、当然、クマ被害とは無縁の、都会的な生活を送ることができているわけですが…
そんな「安全地帯」から、クマ被害で苦しむ自治体や、そこで住民の命や生活を守るために頑張る狩猟者の皆さんに心無い声を浴びせるというのは、やはり通常の感覚では理解に苦しむものがあります。
駆除したクマをジビエ化する取組も
ところで、駆除されたクマも、多くの愛護団体の人たちが主張するように、大切な命であることは疑いようがありません。
そこで、駆除されたしまったクマの命を、せめて大切にいただこうということで、
が進められています。
ジビエとは、狩猟によって捕獲された動物の肉のことで、昨今、ブームとなっています。
たとえば、北海道で、牛を襲い続けて駆除されたヒグマ「OSO(オソ)18」については、駆除されたのちに、食肉として、飲食店や販売業者に卸されていました。


有害鳥獣のジビエ化については、クマのほか、ニホンジカやイノシシ、さらには最近だと千葉県で問題となっているキョンなどでも話題になっています。


熊肉のジビエは、ふるさと納税の返礼品となって、自治体の地域活性化に貢献している事例も多々あります。
ジビエ化は、クマ被害に苦しんでいる自治体が、動物の命に向き合っているからこそ出来る取組だと言えるでしょう。
まとめ
以上、本日は、昨今話題になっているクマ被害について、
- クマ被害が増加する背景
- 北海道東北知事会の緊急要望
- 愛護団体からの苦情電話問題
- ジビエ化の取組
といった、いくつかの視点から、お話させていただきました。
山間部で暮らしていた経験がある方なら、かなりリアルに実感いただけると思うのですが、クマ被害が増加する状況、クマが人間の居住エリアに降りてくる状況の恐怖は、本当に相当なものです。
だからこそ、そこに住む人々の命と生活を守るためには、クマの駆除は必要なことである…当事者の経験がある私は、これが真実だと確信しています。
一方で、クマ愛護団体や、そういった団体と考え方を一にする人からは、クマ駆除に取り組む自治体に対して、連日心無い苦情が大量に寄せられ、自治体の業務妨害となっています。
こういった業務妨害については、遠慮なく対応打ち切りなど、毅然とした対応をとれば良いと考えていますが…
一方、でそういった苦情の背景にある「命の大切さ」というものに、もし思いを馳せるのであれば、「肉をおいしくいただく」という形で、その命を無駄にしないための取組にも力を入れていくことも重要だと思います。
クマ問題、さまざまな論点があり、また感情的・感傷的になりやすいファクターも含まれていることから、議論が激しくなりがちですが…
とにかく、
私たち地方自治にかかわる人間にとって一番大切な視点は、「このまちに住む人々の命と生活を守ること」。
これを胸に、一連のクマ問題に、向き合っていこうと思います。