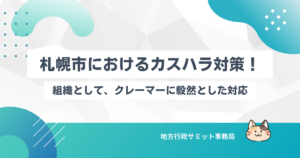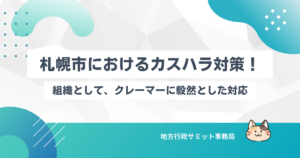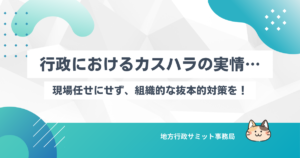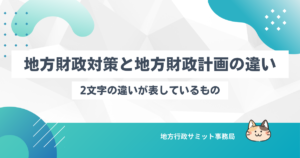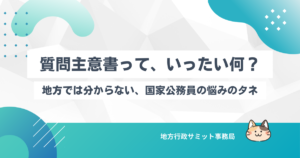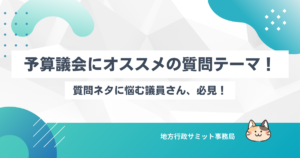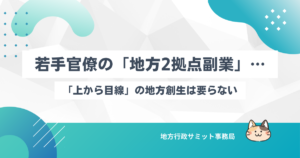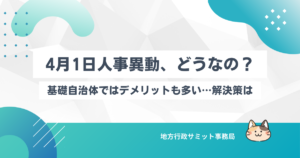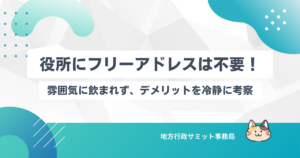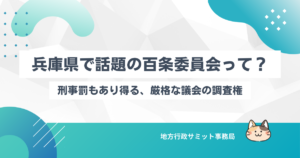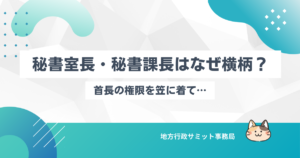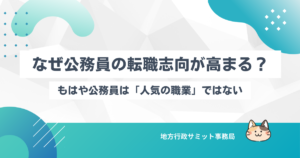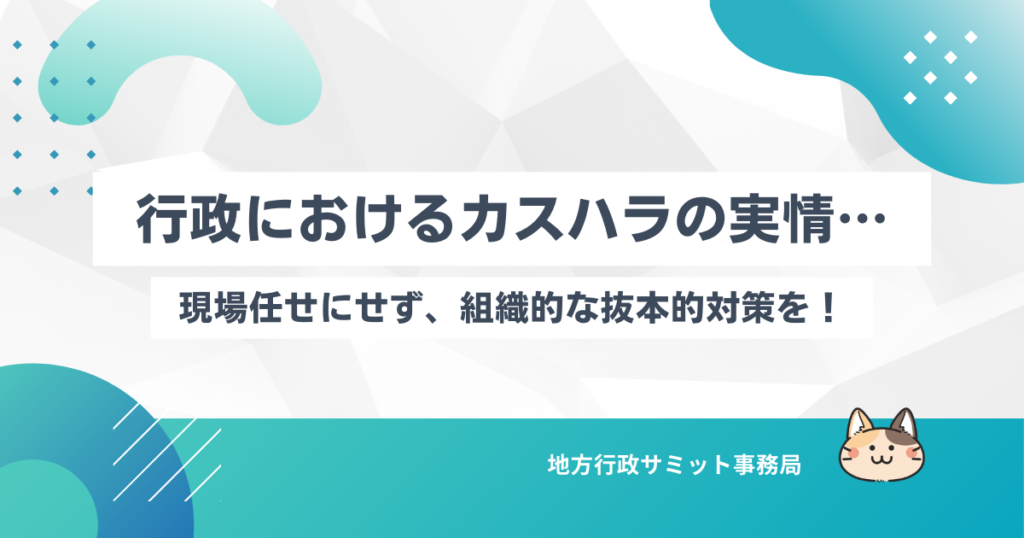
【この記事で分かること】
- カスハラ(カスタマーハラスメント)とは
- 行政におけるカスハラの現状
- 広報・広聴部門で特に多いカスハラの状況
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、行政におけるカスハラ(カスタマーハラスメント)について、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子行政へのカスハラで、地方公務員は本当に疲弊しているのにゃ…
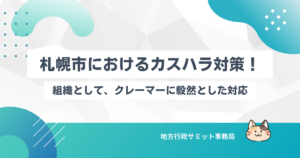
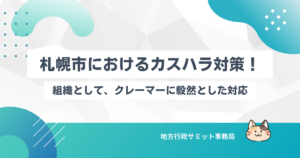
注目されるカスハラ対策
行政職員をやっていると、乱暴な言葉を投げかける住民、何度も訪問して長時間居座る住民など、度を超した住民対応に悩まされることも多いと思います。
こういった、過度なクレームを入れる人たちのことは、「モンスターカスタマー」と呼ばれ、従業員等への過度なクレームも「カスタマーハラスメント」、通称「カスハラ」として注目されるようになりました。
もちろん、こういったクレームが本来業務の支障となる現象は、行政や自治体のみならず、民間企業等でも多々見られます。
ただ、民間では、こういったカスハラ対策は積極的に取り組まれているにもかかわらず、
行政の方はというと、どうもそういったカスハラ対策が及び腰になっているところが多い
のが実情です。
なぜ、行政のカスハラ対策は進まないのでしょうか…。
民間におけるカスハラ対策は進んでいる
冒頭にも述べましたように、こういった「モンスターカスタマー」「カスタマーハラスメント」への対策は、民間企業では強い課題意識のもと、積極的に取り組まれています。
民間企業の場合、たとえば店内で怒鳴る客がいると、
- 他の客が不安になって客足や売り上げに影響が出る
- 過度なクレームに対応している時間が機会損失になる
- 従業員の安全確保や就労意欲にも課題が出る
といったことから、
です。
ですので、たとえば
- 毅然とした態度で「対応しない」旨を通告する
- 事実確認のため証拠となる録画・録音を行う
- 暴力・暴言事案については、警察や弁護士に相談する
などの対応に、積極的に取り組んでいます。
また、厚生労働省も、カスタマーハラスメント対策企業マニュアルや対策リーフレットなどを公表するなど、民間企業におけるカスハラ対策についてはかなり機運が高まっている状況です。
行政の世界におけるカスハラ対策
一方、公務員の世界はどうか。
実は、公務員の世界では、国・地方ともに、カスタマーハラスメント対策に取り組んでいる状況は、民間に比べると動きが鈍いのが実情です。
国の方では、人事院も各府省の官房も、パワハラ対策の中でカスハラ対策に触れている記述はあるものの、カスハラに特化して取り組んでいる様子は、あまり見受けられません。
同様に、地方の方もなかなか動きが鈍かったのですが、令和6年(2024年)6月21日付けで「地方公務員における各種ハラスメント対策の徹底について」という総務省公務員部長通知が出され、この中で「顧客等からの著しい迷惑行為の防止に関する取組」ということで、カスハラに関して具体的な項目が立てられるようになりました。
「地方公務員における各種ハラスメント対策の徹底について」(抄)
3 顧客等からの著しい迷惑行為の防止に関する取組
顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)の防止対策については、パワーハラスメント防止指針においては、事業主が行うことが望ましい取組とされている。
一方、国家公務員については、「人事院規則10-16(パワー・ハラスメントの防止等)の運用について」(令和2年4月1日職職-141)において、行政サービスの利用者等からの言動で、その対応を打ち切りづらい中で行われるものであって、業務の範囲や程度を明らかに超える要求をするものに関する苦情相談があった場合に、組織として対応し、その内容に応じて、迅速かつ適切に職員の救済を図ること
が各省各庁の長の責務とされていることを踏まえ、地方公共団体においても、同様の対応を行っていただきたい旨を令和5年12月通知等により要請を行ってきた。
令和5年調査結果によれば、「他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為に関する取組」については、都道府県や指定都市においては全て措置済みとなっているものの、市区町村においては40.4%(695団体)が未措置となっており、未措置の市区町村においては、速やかに必要な措置を講じていただきたいこと。
顧客等からの著しい迷惑行為を抑止するに当たっては、当該行為の防止を呼び掛けるポスター等を掲示することも有効と考えられるため、例えば、厚生労働省が作成したポスターを地方公共団体の窓口に掲示するなど、各職場等の状況に応じて、抑止に向けた啓発活動に取り組んでいただきたいこと。
なお、顧客等からの著しい迷惑行為の対応に当たっては、厚生労働省が公表している民間企業向けのマニュアル等も参考となるため、御活用いただきたいこと。
(厚生労働省ホームページ「カスタマーハラスメント対策啓発ポスター」)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
の「顧客等からの著しい迷惑行為(いわゆるカスタマーハラスメント)について」の「カスタマーハラスメント対策啓発ポスターはこちら。」を参照。
(厚生労働省ホームページ「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000915233.pdf
※https://www.soumu.go.jp/main_content/000954171.pdf
また、総務省公務員部が事務局を担っている「社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会」という会議体においても、「働き方分科会」の中でカスハラについての議論がなされており、遅まきながらも、少しずつ議論が始まってきている印象です。
住民対応部署などでは対策も見られるが…
次に、地方の現場におけるカスハラの状況を見ていきます。
地方自治体全体での大きなカスハラ対策はまだまだ検討中の状況ではありますが、各自治体の現場では、部署単位で何らかの対策がとられていることがあります。
たとえば、税務などのように、公権力を行使して不利益処分を下せるような職場では、相対する住民と対立することが予想されます。
また、福祉部門や公営住宅部門、公園部門などもトラブルが多いところ。こういったところでは、たとえば警察OBを配置して、高圧的・攻撃的な住民への対応に備えるなど、リスクの高い部署ではカスハラ対策と呼べるものが整っています。


広報・広聴部門ではカスハラ対策がない…
一方で、そうした「カスハラ対策」を全くとらず、無策で「打たれっぱなし」になっている部署も多いのが実情です。では、どのような部署がそういった「無策」に陥りがちなのか…。
よく聞くのは、
広報・広聴部門
です。
住民の方が、広報物などを見て、その内容が気に入らない、あるいはデザインが気に入らないなどの思いをもって、広報・広聴部門にクレームを言いに行く。
はじめはきちんと話を聞くのですが、住民は話を聞いてもらえることに気をよくして、何か新しい広報物が出るたびに役所を訪問して、担当者を1~2時間は説教し続ける。
繰り返しの訪問は、カスタマーハラスメントに該当する旨、厚生労働省のカスタマーハラスメント対策企業マニュアルには、明示されています。
2.リピート型
●理不尽な要望について、繰り返し電話で問い合わせをする、または面会を求めてくる。
ですので、度を越した複数回の訪問は、民間企業であればカスハラとして対応することが一般的なのですが、役所の…それも、広報・広聴部門の場合、「話をしに来た住民の話を聞くことが仕事」という側面もありますので、「カスハラ」としてシャットアウトすることにためらいがあるとの話は、よく聞こえてきます。
そして、クレーマー的な住民は、そういうところも見透かして来ているところがあるから、タチが悪いんですよ…
カスハラ対策は現場任せにせず総務部門で旗振りを
今回は、広報・広聴部門でカスハラの事例をご紹介しましたが、こういった「度を越した複数回の訪問⇒高圧的な説教」のパターンは、部門を問わずに、どこでも起こりえる話です。
そして、日常的にクレーマーとの対応をしている部署でない限りは、こういったカスハラへの対応を組織として行うことができず、結果として職員が疲弊してしまう…という状況に陥ってしまいます。



別記事にしているけど「クマ駆除に関する苦情」は典型的なこのパターンなのにゃ。
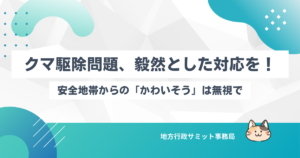
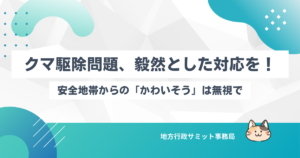
一方で、「クレーマーの多い部署では自発的にできているんだから、部署単位で対策を考えたらよろしい」というふうに、
対応を各部署任せしてしまうと、先述の広報・広聴部門のように「話を聞くことが仕事」のところでは対処方針を考えることが組織ミッションと逆行するようなことになり、抵抗感が生まれてしまう…
というふうになってしまいます。
そこで、公務員におけるカスハラ対策については、
まずは役所の総務部門が、部署を問わずに、毅然とした対応をできるようなマニュアルを整備する
といった動きが必要なのではないかと考えています。
カスハラ対策については、組織として取り組むことが重要です。そして、その「組織」は、できる限り大きくあることが望ましい。
なので、「部署単位」という、最小単位の組織ではなく、「役所の総務部門」という規模で、部局横断的に対応する。
そして、さらに言うと、複数の役所が同じような対応をできるよう、総元締め的な存在である人事院や総務省公務員部がそういった動きを支援していく…ということが重要なのです。
民間企業におけるカスハラ対策は、厚生労働省が一定の考え方を示していることが、各企業の後ろ盾になっているという話もあります。
人事院や総務省公務員部は、まさにそういった役割が求められていると言えるでしょう。
まとめ
以上、本日は、公務員のカスハラ対策についてお話しさせていただきました。
民間企業の方ではカスハラ対策が進んでいますが、役所ではまだまだ取組は十分に進んでいるとは言えません。
その背景には、役所というのは、広報・広聴部門に代表されるように「住民の声を聴く」ことが仕事になっている、という面もあるように思います。
しかし、それを言い訳に、
カスハラ対策を放置しておくと、職員はどんどん疲弊していき、そのことが役所全体のパフォーマンスを下げ、ひいては住民福祉の悪化につながりかねない
のです。
行政課題が複雑多様化する中、公務員一人一人が、モチベーション高く職務に取り組める環境を作ることは、すべての役所共通の課題です。
ぜひ、各役所の総務部門は、分野横断的なカスハラ対策の方針を。
そして人事院や総務省公務員部におかれては、各役所がそういったカスハラ対策に取り組むことを促す取組を。
こういった、組織として職員を守るための取組を、積極的に仕掛けていっていただきたいと思います。