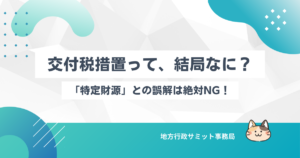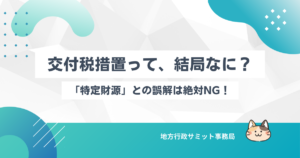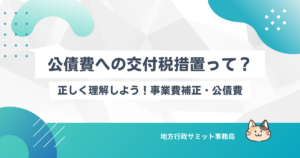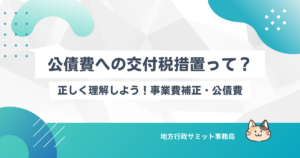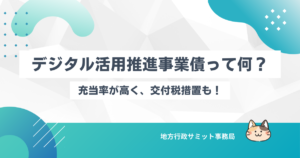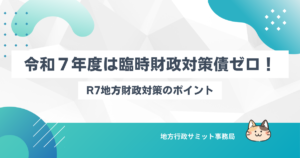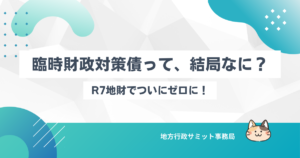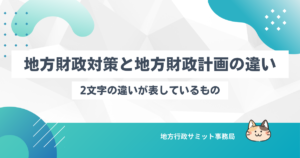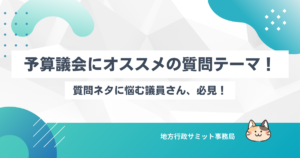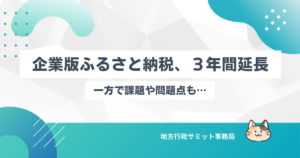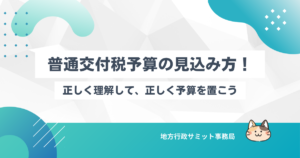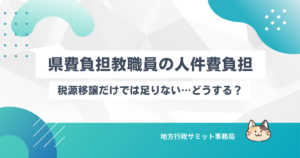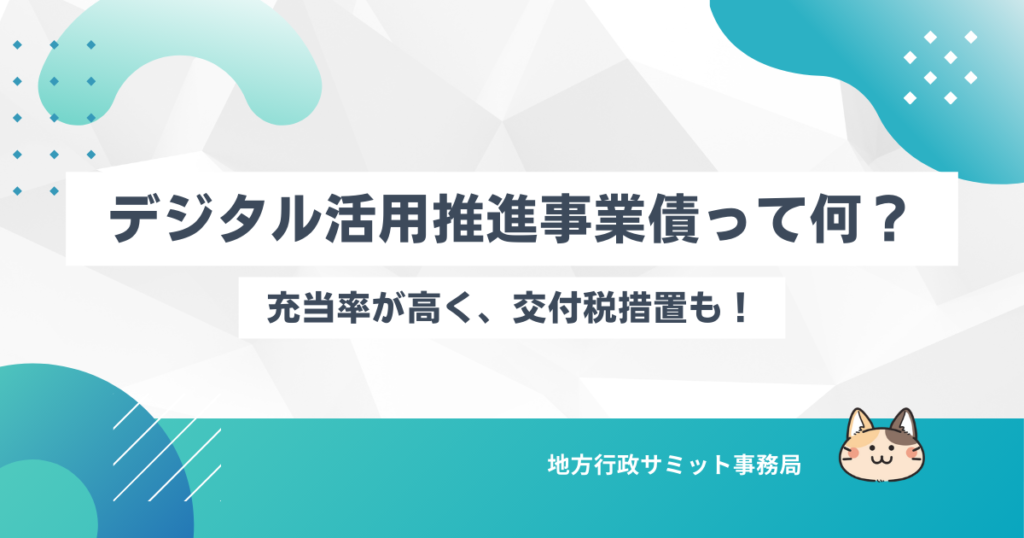
【この記事で分かること】
- デジタル活用推進事業債とは何か
- デジタル活用推進事業債の充当対象事業は何か
- デジタル活用推進事業債の活用にあたっての心構え
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、令和7年度地方財政対策において創設された「デジタル活用推進事業債」について取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子デジタル関係経費の財源に悩む地方自治体財政課の救世主になるかもしれないにゃ。
デジタル活用推進事業債の創設に至る経緯
近年、大幅な人口減少に対応し、担い手不足を解消しながら行政サービスの質や利便性をより高めるため、地方公共団体のデジタル化・DXに対する取組の強化が求められています。
一方で、こういった取組においては、特にシステム整備に要するイニシャルコストが高額となり、これが予算編成における大きな支障となって、財政課の査定がなかなか通らない…といった事案が、各自治体で続出していたようです。
予算編成における財源のやりくりが窮屈な中、デジタル化は「今予算をつけないと世の中が終わる」ような経費ではないですから、査定はどうしても厳しくなってしまいます。
そうした流れの中、令和7年度の地方財政対策に向けて、地方財政審議会がとりまとめた「今後目指すべき地方財政の姿と令和7年度の地方財政への対応等についての意見」において、
を検討すべきである、といった考え方が示されました。
2.効果的・効率的な支出の推進
(1)デジタル化の推進
①地域におけるDXの推進
(中略)以上のように、自治体DXや地域社会DXの取組は、地域の担い手不足が深刻化している中で、官民の生産性を高めていくために不可欠であり、かつ、緊急に進めていく必要がある。一方で、集中的にデジタル化を進めるためには、情報システムや情報通信機器を整備することが必要となるが、その際に、初期経費が大きくなるといった課題もある。このため、初期経費の負担を平準化するため、地方債の発行を可能とする特例措置を講じることを検討すべきである。
※地方財政審議会「今後目指すべき地方財政の姿と令和7年度の地方財政への対応等についての意見」より
これを受け、総務省自治財政局において検討がなされ、令和7年12月27日に示された令和7年度地方財政対策において、
デジタル対策推進事業債(仮称)
が創設されることとなったのです。


デジタル対策推進事業債とは
さて、そんな「デジタル対策推進事業債」とはどのようなものか、現時点で判明している情報をもとに、ご紹介していきましょう。
基本的な考え方
デジタル対策推進事業債の基本的な考え方は、令和7年度地方財政対策のPRペーパーに示されています。
担い手不足が急速に深刻化するおそれがある中、デジタル技術を活用した行政運営の効率化・地域の課題解決等に向けた取組をしていくため、「デジタル活用推進事業費(仮称)」を創設。地方財政法の特例を設け、情報システムや情報通信機器等の整備財源に活用できるデジタル活用推進事業債(仮称)の発行を可能とする
どのような考え方で地方債を充当できるようにするかは、いくつかの考え方があるように思いますが、このペーパーを見る限りにおいては「地方財政法の特例を設け」とありますので、地方財政法の改正を通じて適債化しようとしているといった理解ができそうです。
地方財政計画・地方債計画における計数整理
上記に書かれている「デジタル活用推進事業費」ですが、こちらは地方財政計画の歳出において、一般行政経費(単独)の一部として、1,000億円が計上されています。



いわゆる「一行単独(いちぎょうたんどく)の内数」ってやつにゃ。
そして、その財源として、地方債の「デジタル活用推進事業債」が歳入に計上されるのですが、その金額は900億円。後述するように、本地方債は充当率が90%とされているので、1,000億円×90%=900億円が歳入としてカウントされている、というわけですね。
この900億円は、地方債計画の方にも反映されています。
充当対象事業はどのようなものか
デジタル活用推進事業債の充当対象事業としては、次のようなものが挙げられています。
(1)行政運営の効率化・住民の利便性向上を図る自治体DXの推進
これは、
① システムの導入(初期経費)
ア 住民サービスの提供に必要なシステムの導入
イ 共同調達によるシステムの導入
② 情報通信機器等の整備
ア 住民利用の情報通信機器、住民サービスの提供に必要な職員利用の情報通信機器の購入
イ 公共施設のネットワーク環境の整備
といったものが想定されています。
たとえば「書かない窓口」や「オンライン申請」の導入にかかるイニシャルコストなどが想定されるところですが、各自治体が具体的に想定する事業については、上記のような考え方に当てはめられるかどうかがポイントとなりそうです。
また、「住民サービスの提供に必要な職員利用の情報通信機器」というのが結構興味深く、たとえばペーパーレスの取組に必要なタブレットや公用スマートフォンの導入なども充当対象経費として想定できるのかな…と踏んでいます。
(2)地域の課題解決を図る地域社会DXの推進
こちらは、
地方団体及び公共的団体等による地域の課題解決に資するシステムの導入及び情報通信機器等の整備
(地域の課題解決)
・ 医療、交通等日常生活に不可欠なサービスの確保
・ 農林水産業、観光など地域産業の生産性向上 等
といったものが挙げられています。
たとえば、人口減少エリアにおいて特にニーズの高いオンライン診療や、いわゆる「スマート農業」の推進に要する経費などが想定されるところです。



クマ、シカ、イノシシといった有害鳥獣の捕獲のとき、トレイルカメラがあるとすごく便利なので、こういった経費にもぜひ充当できるようにしてほしいにゃ。
ただ、これらは行政が持つものというよりは、住民が使うものになるだろうから、どういうスキームにすると良いのかは悩ましいところですよね。
本来だったら非適債の住民向け補助事業にも適債性を認めるため、地方財政法の改正が必要、ってことなのかなあ…。
詳細な情報は、総務省の都道府県財政課長会議で出ているみたいだから、そちらを合わせて見ても良いかもね。
システム標準化に要する経費は対象外!
なお、このデジタル活用推進事業債ですが、
地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づく標準化のために必要な経費を除く
と、標準化に要する経費は充当対象外であるということが、はっきりとPRペーパー上にも書かれています。
標準化に要する経費は本来的には全額国庫負担とされていることから、こういった考え方が示されているのでしょうが、一方で本当に全額が国庫負担で対応できるかどうかについては未だ予断を許しません。
現実問題として地方負担が生じてしまうのであれば、そこは少しでも有利な財源を確保したいというのが財政課の偽らざる本音でしょうが、現時点においては、このような考え方が示されている点、留意が必要です。
自治体の財政運営的には、ここが一番アタマが痛いところなんですけどね…。
デジタル活用推進事業債の充当率と交付税措置
今回のデジタル活用推進事業債については、国が主導的に創設した地方債であることからか、かなり手厚い地方財政措置が講じられています。
まず、充当率は90%。一般的な単独事業、いわゆる「一般単独」の充当率が75%であることを考えると、この90%は相当に高い充当率です。
そして、地方債を発行すると、後年度に公債費(借金の返済)が発生することになりますが、その公債費相当額については、後年度に交付税措置が講じられることとなっており、その交付税措置率は50%と、かなり高い設定になっています。
公債費にかかる交付税措置は、原則として基準財政需要額に相当額が+αで加算されるものなので、これが個別団体の財政運営に与える影響は、非常に大きいです。



既に一般財源充当で予算査定を終えた事業も、場合によっては財源振替を考えても良さそうなのにゃ。
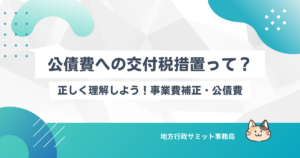
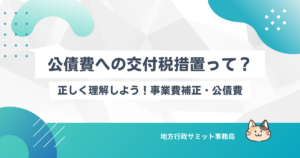
【注意】有利な財源だからといって不要な事業をしないように
今回のデジタル活用推進事業債は、充当率90%、交付税措置率50%という非常に有利な地方財政措置が講じられており、
国として、地方のデジタル化・DX化を推進したい
という、政府の強いメッセージを感じます。


地方自治体にひそむ「デジタル化ありき」の勢力
一方で、地方自治体の現場に立つと、



本当に必要かどうかは疑わしいんだけど、最近基幹システムのベンダーが「時代の流れ的にこういうシステムが要りますよ」とうるさいんだよな…
とか



民間のシステム会社から外部登用したCIO補佐官が、「あれもやれ」「これもやれ」と、現場が必要としないシステムの導入をやたら急かすんですよね…
といった声が、非常に強く聞こえてきます。
「デジタル化ありき」の勢力に利用されないように
国策としてデジタル化・DX化が進んでいるということについて異論はありませんが、一方でこういった動きが起こる背景には、
デジタル化・DX化を通じて一儲けしたい事業者や、存在感を発揮したいデジタル系の有識者が存在する
という事実も押さえておかなければなりません。
住民の利便性が高まったり、行政の効率性が高まったりする取組はもちろん推進すべきなのですが、一方で
- 実際の活用イメージがなく、「やってる感」を演出するだけの取組
- 利便性は高まるが、その割に予算額が高く、費用対効果に疑義のある取組
- ベンダーや外部登用人材がごり押ししてくる取組
といった、「自治体が住民の税金を使って行うべきか疑わしい取組」までもを、有利な財源があるからといって実施する必要は、全くありません。
いくら有利な地方債だといっても、その交付税措置率は所詮は50%。てことは、残りの50%は政策財源(留保財源)対応をさせられるわけですから、結局は自治体の純然たる負担になってしまいます。
また、最近は人手不足の時代ですから、有効性が疑わしい事業に職員を割いている余裕はないのです。
もちろん、「必要性は認めるけど、財源がなあ…」といった取組については、ぜひこのデジタル活用推進事業債を使っていけば良いと思います。
要は、
有利な財源があることと、「そもそもその事業が必要かどうか」の判断は、全く関係がない。
不要な事業はたとえ有利な財源があっても、遠慮なくゼロ査定して良い。
ということです。
いわゆる「政商」みたいな人たちや、そこに籠絡されたデジタル部門の職員が、デジタル活用推進事業債のPRペーパーを片手にごり押し営業が来ることのないように注意したいですね。



もしそんなのが来たら、財政課や事業原課のみんなは、この記事を片手に対抗してほしいのにゃ!
まとめ
以上、本日は、令和7年度地方財政対策において示された「デジタル活用推進事業債」について解説させていただきました。
デジタル活用推進事業債は、これまで一般財源対応を余儀なくされていたデジタル関係のイニシャルコストに対して充当できる地方債で、しかも後年度に50%の交付税措置がついてくるという、とても有利な地方債です。
一方で、地方自治体まわりには「デジタル化ありき」の勢力がビジネスチャンスや存在感確立のためにひそんでおり、この財源がそういった人たちに「利用」されて、不要な事業をさせられたりしないように留意する必要があります。
とはいえ、「必要な事業があるけれど、財源だけが悩み」というところも多いかと思いますので、そういった案件においては、この地方債が活躍すること、間違いなし。
デジタル活用推進事業債、事業内容をしっかり精査しながら、積極的に活用していくと良さそうですね。