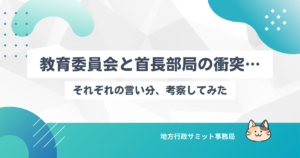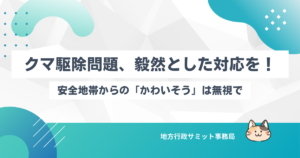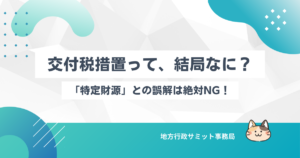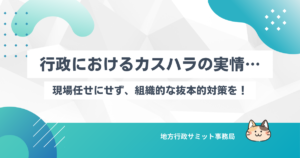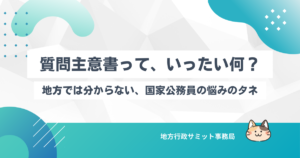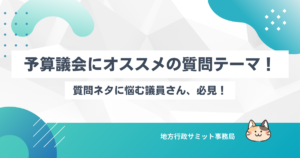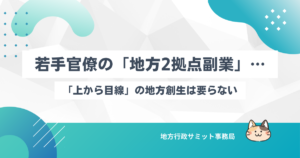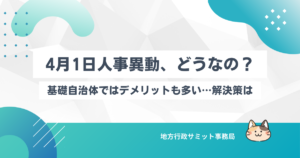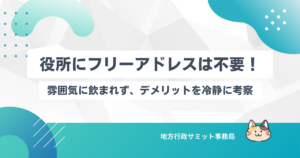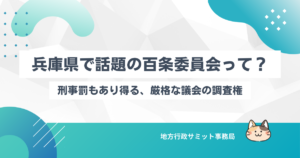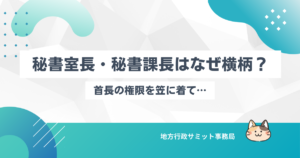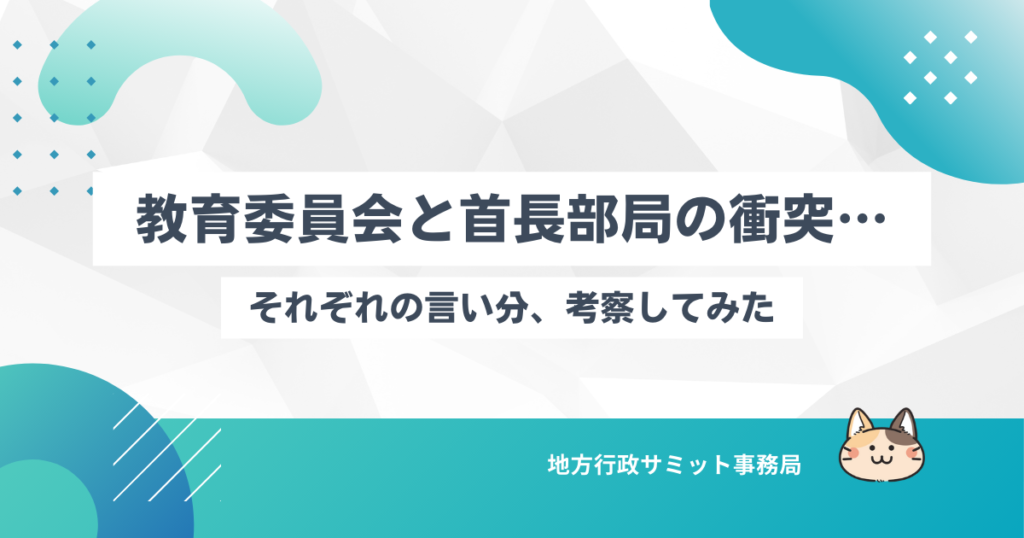
【この記事で分かること】
- 教育委員会と首長部局の対立構造
- なぜ教育委員会と首長部局の調整は難航するのか
- どのようにすれば教育委員会と首長部局はうまくやれるのか
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、いつも衝突しがちな教育委員会と首長部局の関係性について、取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子教育委員会と首長部局の関係性は、都道府県・市区町村を問わず、どこも同じような感じみたいなのにゃ。
いつもトラブる教育委員会と首長部局…
地方自治体の首長部局…特に総務や財政などの全体調整系の部署で仕事をしていると、困るのが教育委員会事務局との調整。
政策調整にしても予算査定にしても定員管理にしても、首長部局の常識が通用せず、非常に苦労することが多々あります。



だから教育は…



また教育か!
みたいなグチが聞こえてくることは、しょっちゅうですよね。
一方、教育委員会事務局の側は、そういった首長部局側の苦労は今ひとつピンときていませんし、何なら



首長部局が邪魔ばっかりしてきてくるせいで、理想の教育が追求できない!



首長部局の連中は、子どもがどうなってもいいと思っている!
みたいな感じの対立構造に陥りがちです。
いったい、なぜ、教育委員会事務局と首長部局の調整はうまくいかないのでしょう…。
そもそも教育委員会とは
この議論に入る前に、そもそも教育委員会制度とは何なのか。
文部科学省のこども向け解説ページに、わかりやすく書いてあったので、そちらから引用してみます。
教育委員会は、全ての都道府県・市区町村に置かれており、複数の教育委員で構成されています。その組織は、かたよった教育がなされることを防ぐため、知事や市町村長から独立したものとなっています。
たとえば、学校を設置すること、先生の人事や研修、校舎の整備、学校で使用する教科書選びなど、その街の教育について大切なことを教育委員会の会議で決定します。
ほかにも、図書館や博物館の設置やその街の文化財の保存、活用なども教育委員会の仕事です。
この解説のポイントは、
教育委員会は、知事や市町村長から独立している
ということ。
過去の様々な歴史的経緯の中で、教育行政については、首長部局から切り離され、これを担う教育委員会は、制度上は独立した組織となっています。
同じように、選挙管理委員会も首長部局から独立していますね。
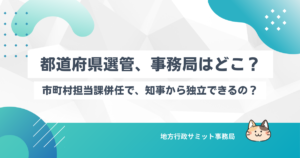
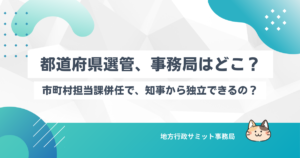
建前は「独立」…一方で実務上は影響を受ける教育委員会
ただし、教育行政において必要となる予算の編成権は首長部局にあります。
また、一般に教育委員会事務局の職員は、首長部局で採用された職員が出向することも多いです。
なので、制度上は「首長部局から独立した」という立て付けになっている教育委員会ですが、実務上は、首長部局の影響を大きく受けざるを得なくなっています。
なぜ教育委員会との調整はうまくいかないのか
と、このように見ると、実態として教育委員会は「首長部局の中の一組織」というような形に思えるのが現実です。
少なくとも、首長部局で全体調整をしていると、どうしてもその錯覚に陥ってしまいます。
でも一方で、教育委員会は、首長部局の全体調整の中では、どうしても異質な存在となり、言葉を選ばずに言うと「言うことを聞かないわがまま組織」となりがちです。
以上を前提とした上で、
「なぜ教育委員会と首長部局の調整はうまくいかないのか」
検討してみたいと思います。
【理由①】教員出身の事務局職員に俯瞰的な視点がない
教育委員会事務局の職員は、先ほど書いたように、多くの職員が首長部局からの出向で構成されています。
一方で、職員の中には、学校現場の先生が「指導主事」という形で教育委員会事務局に席を置いているパターンもあります。
この「指導主事」は、多くの場合、教育委員会事務局における学校教育の統括部署に配置されます。
そして、学校現場での経験を活かしながら、学校教育分野の政策を作り上げていくことが求められます。
なるほど、確かに、指導主事の先生方は、学校現場の実情については優れた知見をお持ちでしょう。
しかし、一方で、
学校現場のことしか知らない先生方は、自治体の予算制約のことや、行政全体を見据えた政策調整については、全く知識・経験がない
というのが現実です。
学校教育といえば、教育行政のまさに核となる部分で、政策・予算ともに議論の中心がここになりますが、その部門において、全体を俯瞰的に見る経験を持たない、教員出身の指導主事が支配的に業務を遂行すると、
学校現場現場の理屈だけで作られた、俯瞰的な視点のない政策
が出来上がってしまいます。
そのため、首長部局の査定部門がそういった政策を見た際に、俯瞰的な視点や有限資源の制約といった課題意識から、教育政策について厳しい査定を下すことがありますが、そういった視点でものを見る経験が乏しい教員出身の職員たちは、



査定部門が何を言っているか分からない
となり、ただ一方で、「予算カット」「新規事業不採択」という事実だけは厳然と残りますので、教育委員会サイドには



首長部局が訳の分からない理屈で私たちのやりたいことの邪魔をする
というふうに思われてしまい、こういった事実の積み重ねが感情的なしこりとなって、教育委員会と首長部局の円滑なコミュニケーションに支障を生じさせるのです。
【理由②】学校現場を教育委員会が統制しきれない
先ほどの「理由①」は、主に教育委員会と首長部局の対立構造について論じていますが…
一方で、教育委員会内部にも、さまざまないざこざがあります。
その最たるものが、「学校現場を教育委員会が統制できていない」という問題です。
教育行政の最前線に立つのは、言うまでもなく学校なわけですが、学校は教育委員会の下部組織というわけではなく、現場感覚的には、
という様相を呈しています。


もちろん、人事的な話とか、予算執行の話になると、教育委員会事務局を通してでないと話ができないので、そういった点における教育委員会の影響力は残せているのですが…
一方で、それらを除く、日々の学校運営における影響力としては、校長は絶大なる存在感を発揮しており、教育委員会ですら、その影響力を軽んじることはできません。
なので、新しい政策を作って、学校現場で運営しようと思っても、たとえば1人でもその政策に反対の校長先生がいると、実現ができなくなってしまうのです。
より具体的な例を出すと、たとえば、



学校で配るプリントの扱いに保護者が困っているようなので、これをペーパーレスにして、保護者のスマホで見られるようにしましょう!
という政策を作ろうと思っても、たった1人の校長が



それを保護者に説明するのは誰だと思ってるんだ!余計な仕事を増やしやがって!わしは絶対にそんなのやらんからな!
と強硬に主張すれば、その政策をボツにしてしまえるほどなのです。
このように、教育行政の現場は、校長先生にかなりの影響力がある状況であり、それゆえに教育委員会は現場を統制しきれていないという事態に、よく遭遇します。
【理由③】首長部局の査定担当職員が過度な介入をしている
ここまでは、どちらかというと教育委員会側に批判的な論調で語ってきましたが、一方で首長部局の職員にも問題があるパターンもあります。
序盤に書いたように、教育委員会は、建前としては首長部局から独立した組織ですが、一方で予算編成権などを通じて、首長部局にも一定の間接的な影響力があります。
しかし、担当職員の中には、この「間接的な影響力」を過度に行使し、教育委員会に過度な介入をしてしまっている者も見られます。
確かに、【理由①】【理由②】で書いたように、教育委員会事務局内には、教育委員会特有の問題点から、うまく政策が作れなかったり、統制が取れなかったりする事案がよく見られます。
一方で、そのことにイライラして、予算編成権や政策調整権を笠に着ながら、教育委員会の職員に罵詈雑言を浴びせたり、組織内外で教育委員会の悪口を吹聴してまわる査定担当職員が存在するのも事実です。
こういった立ち振る舞いは、どの部局に対してであっても、普通に良くない行動でありますが…
それに加えて教育委員会に対してこういったハラスメント的な行動を取ることは、場合によっては「教育行政の独立を侵害」と取られてしまう可能性も十分にあります。
首長部局で査定を担当する職員には、あまり自覚がないかもしれませんが、基本的に首長部局の職員は「首長の補助機関」であり、自身が職務として行った行動は、最終的には首長の名の下に行われたことになります。
そういった事実の積み重ねが、教育長や教育委員会の事務局長など、教育委員会の幹部の耳に入ると、
首長部局が、教育行政に不当な介入を行っている
となってしまい、教育委員会と首長部局の調整を難航させる要因を作り出してしまうことになるのです。
【提言】教員出身者も首長部局の査定部門を経験すべき
このように、教育委員会には教育委員会の問題が、そして首長部局の査定チームにはそちら側の問題があるのですが…
いずれにせよ、教育委員会と首長部局の調整は、いつの世も難しいもの。
そこで1つ提言があります。


それは…
教員出身者にも、首長部局の査定部門を経験させる
というもの。
教員出身者は、教育現場のことについては高い専門性を有しますが、一方で政策全体を見据えた調整というのは、経験がなく、そのことが教育委員会と首長部局の調整を困難化させています。
そこで、教育行政全体を担える…もっというと、教育委員会事務局の幹部を担えるような、将来有望な教員出身者については、まずは早めに首長部局に出向させましょう。
そして、首長部局では、企画・政策部門や総務部門など、全体調整を担う仕事に従事してもらいます。
このことにより、
ということを実感してもらい、その実感を教育委員会に戻った後に、その業務に活かしてもらうのです。
もちろん、いきなり首長部局の企画・政策部門や総務部門に送りこむというのは、相当にハードルが高いと感じられるかもしれません。
その場合、たとえばまずは教育委員会事務局の総務課に置くなどして、部局内の総合調整から担ってみる、というのもひとつの手でしょう。
とにかく、「教育現場しか知らない」「教育行政しか知らない」という、悪い意味で専門性を高めてしまう職員がいると、俯瞰的な視野を失って、大きな調整・大きな判断ができなくなってしまいます。
専門性を活かしながら、俯瞰的な視点を持つ。
虫の目と鳥の目の両方を持つ職員を、教育委員会事務局に置くことが、大切なのです。
まとめ
以上、本日は、教育委員会と首長部局の調整の困難さについて考察するとともに、どのようにすればこの状況を解決できるか、思い切った提言についても、お話しいたしました。
教育委員会と首長部局の仁義なき戦いは、どこの自治体でも見られる現象のようで、それぞれの自治体で、それぞれの部局が、日々苦労されています。
それぞれにはそれぞれの言い分があることは重々承知しているのですが、両者が単純に対立しているだけでは、良い政策は作れませんし、子どもたちのためにもなりません。
どうか、両者が建設的な議論を進められるよう、お互いの立場を理解しながら、教育行政の推進に当たれるよう、願っております。