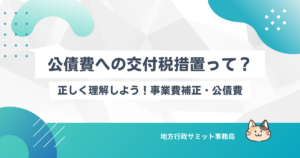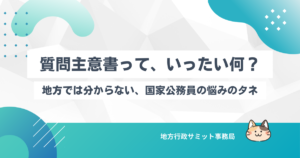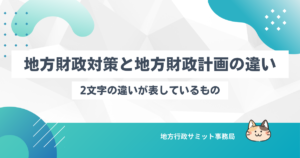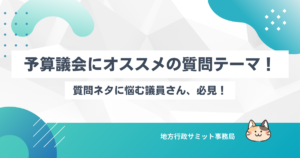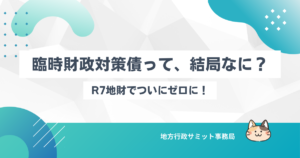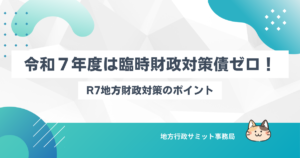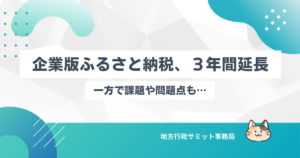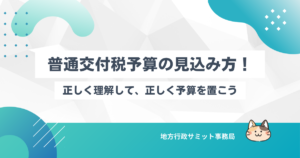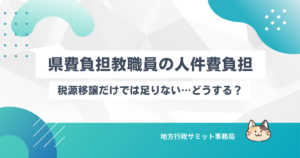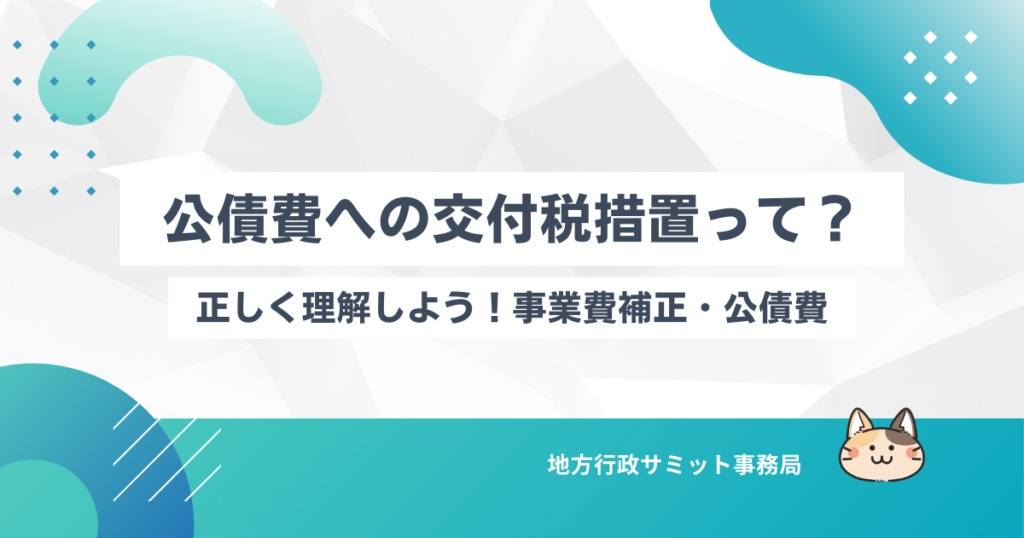
【この記事で分かること】
- 公債費にかかる交付税措置(事業費補正・公債費)の概要
- 公債費にかかる交付税措置の留意点
- 事業費補正と公債費の違い
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、財政について正しく理解する上で欠かせない、公債費への交付税措置について、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子公債費への交付税措置は、財政運営への影響が他の一般的な交付税措置と異なるから、正確に理解する必要があるのにゃ。
一般的な交付税措置=ミクロの財政運営には影響しない
「交付税措置」。国が地方団体に仕事をさせるときに、体よく使ってくる言葉…。
多くの財政課職員が、このような印象をもっていようかと思います。
国の地方向けポンチ絵などを見ていると、あたかも国庫補助金かのようにこの「交付税措置」という言葉が使われていますが、実態は単なる単位費用措置で、個別団体の基準財政需要額が純増になるものではなく、財政運営上のメリットには一切なりません。
このような「交付税措置」に、財政課職員は苦しめられているから、「交付税措置」という言葉に対して不信感をもっている人も一定いるのではないでしょうか。



詳しくは、別記事で詳しく語っているのにゃ。
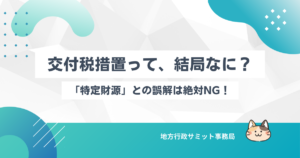
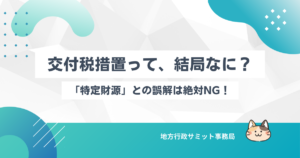
公債費への交付税措置は基準財政需要額が純増になる
ただし、そうした交付税措置は、「各自治体の実情にかかわらず、『人口等の測定単位×単位費用』で機械的に算定するから」、財政運営に影響しないわけですが、例外的に各団体の実情を捕捉して基準財政需要額を加算することもあります。
その「例外」を構成する要素の1つが、
なんです。
公債費の交付税措置は、その多くが、
各団体の地方債発行額または実際の元利償還金を基礎数値として、それに一定の割合を乗じて得た交付税措置額を、基準財政需要額に加算
する形で算定されます。
地方債発行額を基礎数値とする項目は、それに一定の乗数(理論償還条件)を乗じて得た数値を、基準財政需要額に加算。
元利償還金を基礎数値とする項目は、その元利償還金に交付税措置率を乗じて得た数値を、基準財政需要額に加算。
このように、公債費に対する交付税措置は、各自治体の実際の起債額や償還額を用いて算定しているので、
何もしなければ交付税措置額は増えないが、事業を実施して地方債を起こすと、公債費にかかる交付税措置額が純増になる
ということになるのです。



この基準財政需要額の乗っかり方は、個々の自治体単位で見ると、かなり補助金に近いイメージを持てるのだにゃ。
ただ、財政課職員でも、交付税か地方債の実務担当者をやった人でないと、このあたりの感覚は理解できないんですよね。
精神論だけで仕事をしている財政課の査定担当者や、財政制度をろくに勉強していない企画課の政策調整担当が、この辺のことを理解せずに、変な査定をしてることが、多くの自治体でよくあるんだよ…。
「事業費補正」と「公債費」は何が違う?
さて、この「公債費に対する交付税措置」については、技術的には2つのパターンがあります。
1つが「事業費補正」、もう1つが「公債費」です。
事業費補正:公債費相当額を各費目で補正係数化して加算
まず「事業費補正」です。
こちらは、基準財政需要額の関係費目において、公債費相当額を補正係数化して、加算するというもの。公債費相当額をきちんと千円単位の数値で捕捉しにいってはいるのですが、その数値をそのまま加算するのではなく、「事業費補正」という補正係数に変えてから算定する形をとっています。
たとえば学校関係の地方債は小学校費や中学校費で、市町村における一般廃棄物処理施設整備事業債の公債費は清掃費で算定したりします。
なお、上水道事業・簡易水道事業や病院事業にかかる公営企業債の交付税措置額は、「事業費補正」という補正係数を用いず、(保健)衛生費の「密度補正」において行われます。
公債費:基準財政需要額の費目として算定
そしてもう一つ「公債費」という費目で算定する方法。
こちらは、地方債発行額に理論償還条件を乗じた数値や、実元利償還金に交付税措置率を乗じた数値を、そのまま基準財政需要額として算定します。
たとえば、臨時財政対策債の公債費や、かつて存在した減税補てん債などは、このような形で算定しています。
事業費補正:省令事項、公債費:法律事項
と、このようにしてみると、



事業費補正と公債費って、何が違うんだろ?
と思うかも知れませんが、実はこの事業費補正と公債費には、算定上の意味合いが異なるところがあります。
それは、
事業費補正は省令事項である一方、公債費は法律事項である
ということ。
言うまでもなく、「法律事項の方が格上」です。
ですので、交付税措置率が高かったり、公債費にかかる交付税措置に根拠法が存在する臨時財政対策債や公害防止事業債などは、法律事項として公債費費目で交付税措置を行うのですが、そうではない政策誘導系の交付税措置は、事業費補正という省令事項での算定にとどめてたりしています。
地方自治体の立場だと、どちらも得られる効果は一緒なのですが、背景にある考え方を知っていると、地方財政制度への理解も深まるものです。


【注意①】マクロで見ると「財源の純増」ではない
ただし、この公債費にかかる交付税措置については、注意点があります。
まず1つが、
個別の自治体単位でみると、財源の純増に見えるけど、マクロで見ると財源の純増ではない
ということ。
確かに、個別自治体単位で見ると、その自治体が地方債を起こしたか否かによって、基準財政需要額が加算されるかどうかが決まってきますから、この「公債費にかかる交付税措置」は、財源の純増に見えます。
しかし一方で、
マクロの交付税総額は、「地方財政計画の歳出総額」に基づいて決まってくる
ことになりますから、手厚い交付税措置があるからといって、交付税総額が増えるわけではありません。
え、え、どういうこと?
総務省が地方交付税総額を決めるためには、地方財政計画を作りますけど、地方財政計画は「歳入歳出総額の見込額」なんです。そしてそこには、基準財政需要額とかの概念はないんですよ。
てことは、マクロの基準財政需要額ってのはないってこと?
「ない」とまでは言い切れないかもしれませんが、少なくとも交付税総額を決めるときには、そういった概念は一切使われてはいませんよ。
なるほど、だから交付税措置率はマクロには関係ないってことなのか。
そう、極端な話、公債費のすべてが一般単独事業債であっても、逆に全部が緊急防災・減災事業債であっても、マクロの地財計画には全く関係しない、ってことなんです。
マクロでの財源保障は「今そこにある公債費に対して、それに見合う財源が、地方税と地方交付税とで確保されているか」という点しか見ておらず、その公債費に対する交付税措置率はあまり関係ありません。
言い換えると、
交付税措置率は、マクロの地財歳出総額から決まった交付税総額を、各団体にどのように配分するかを決めるにあたって用いている指標
でしかないのです。
公債費にかかる交付税措置は、マクロ(総務省自治財政局)とミクロ(各自治体の財政課)で全く見え方が異なる典型例だろうね。


【注意②】交付税措置率は100%ではない=残りの公債費への対応が必要
そして、注意点はもう1点。
交付税措置は、現在、(臨時財政対策債を除くと)高くても70%までであり、交付税措置されない残りの部分を、留保財源対応しないといけない
ということです。
現在、交付税措置率が特に高い地方債といえば、過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債が挙げられますが、これらの交付税措置は70%。
「70%」と聞くと大きな財源のように感じられますが、逆に言うと、残り30%は、全く交付税措置がないことになりますから、その公債費を支払うための財源を、留保財源(基準財政収入額に算入されない税収の25%分)から捻出しないといけません。
なので、「高い交付税措置があるから」と、調子に乗って地方債を起こしまくると、この「交付税措置されない部分の公債費」で財政運営が苦しくなる…ということが起こってしまうので、注意が必要です。



特に税収の少ない過疎団体では、過疎債の「残り30%」に苦しんでいるところが少なからずあると聞くにゃ…。
最近だと、「デジタル活用推進事業債」でこのトラップにはまる自治体がありそうだから、注意が必要ですね!
一方で、逆に「公債費の交付税措置なんて、財政措置がないも同然」とか主張する脳筋タイプの財政課・企画課職員もいるから、管理職の立場だと、担当者たちへの教育が難しいんだよね。
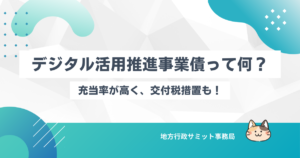
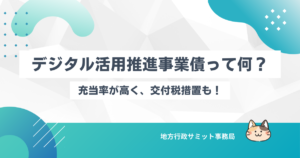
まとめ
以上、本日は、公債費に対する交付税措置について、ご紹介させていただきました。
公債費に対する交付税措置は、他の一般的な交付税措置と違い、各自治体の実際の地方債発行額や元利償還額に対応して基準財政需要額が加算されるしくみであるため、個別自治体の財政運営という視点で見ると、財源が純増となり、上手に活用することで、有利に財政運営を行うことが出来るようになります。
一方、マクロで見ると、財源総額が増えるわけではないので、地方財政全体では必ずしも財政が健全化するわけではないということ、また交付税措置も100%ではないので、交付税措置されない残り部分に対する公債費の対応を考えないといけない点には、注意が必要です。
いわゆる「脳筋タイプ」の財政課・企画課職員は、この「公債費にかかる交付税措置」のことを正しく理解できていないことが多いように思います。
でも、この交付税にかかる交付税措置、正しく理解することが、正しい政策判断、そして正しい財政運営において、非常に重要です。
自治体現場で地方債や交付税の実務をしないとピンとこないところもあるかもしれませんが、ぜひ積極的に、勉強してくださいね!