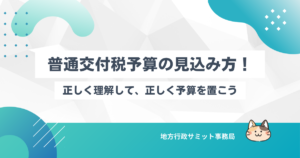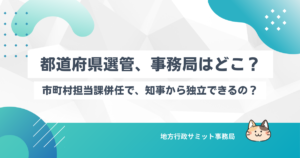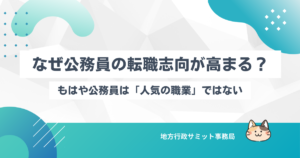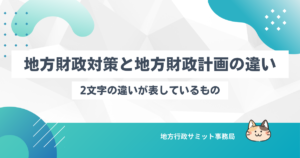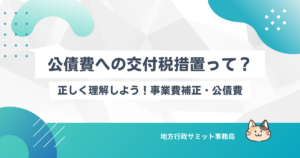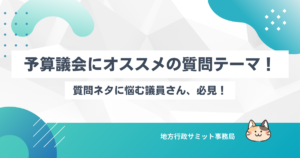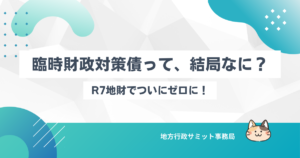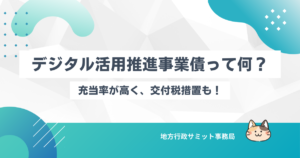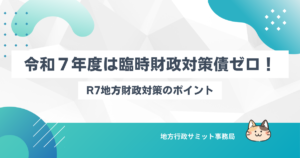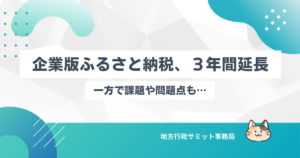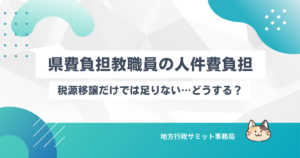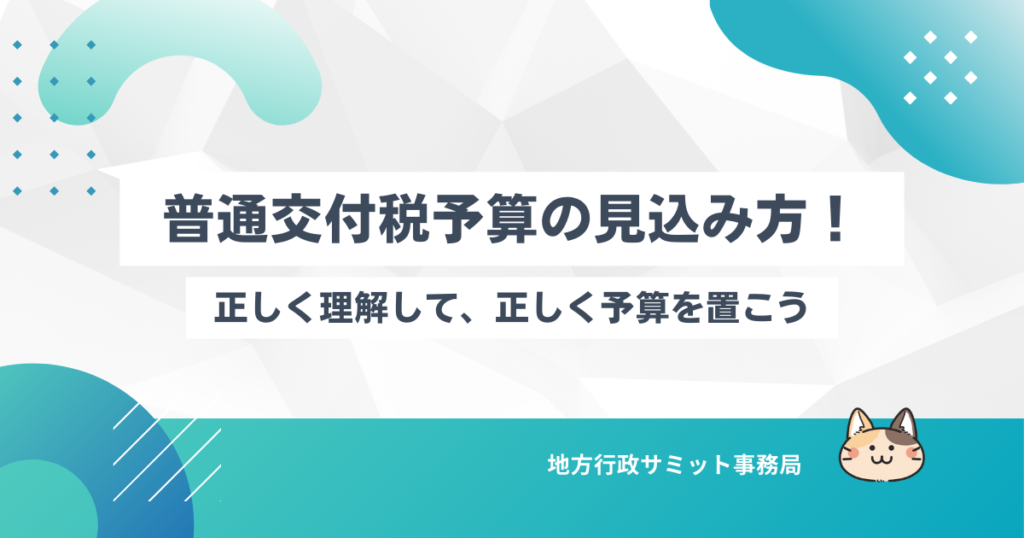
【この記事で分かること】
- 普通交付税(臨時財政対策債)予算の見込み方
- 普通交付税予算を見込むために必要な資料と入手方法
- 交付税予算を見込む上での注意点
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、普通交付税予算の正しい推計方法について、ご説明させていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子普通交付税事務の基本中の基本だけど、交付税担当以外も知っておいた方がいい知識なのにゃ。
歳入予算のカギは普通交付税
各年度の予算編成において、地方税と並んで歳入の根幹となる地方交付税。
その中でも、核となる普通交付税の予算について、どのように計上するか…。
地方交付税制度について一定の理解ができている地方自治体であれば、大きく外すことはしないのですが、この予算をどう見込んでいいか分からず、適当に見込んで予算を大外しし、予算執行において支障が出る事例を、たまに聞きます。



予算の歳入歳出が合わずに、とりあえず謎の理屈で普通交付税を膨らませて、無理矢理予算を組んでいるところがあったりするのにゃ。
ということで、ここからは、普通交付税の予算の見込み方について、ご説明させていただきます。
なお、以降の文章は、地方財政制度についての基礎的な理解を前提としています。言葉や概念が分からないときは、地方財政制度の本などで調べながら読み進めてくださいね。
まずは総務省交付税課資料を入手しよう
この一連の作業を行う上で、絶対に必要になる資料があります。
それが、総務省交付税課が1月下旬の「全国都道府県財政課長・市町村担当課長会議」で配布する、
という資料です。
この資料の中に、後述する「推計参考乗率(指示伸び率)」や、各種費目の考え方など、交付税予算を見込む上で必要となる情報がすべて詰まっています。
この資料は、会議の当日に紙ベースで配布されるほか、iJAMPには当日の課長発言とともに資料が電子データで掲載されています。
また、この資料については、都道府県の市町村担当課が管内市町村に情報展開しており、基礎自治体職員であればそのルートで入手することも可能です。
「全国都道府県財政課長・市町村担当課長会議」の資料の中には、総務省として報道発表で公表しているものと、そうでないものとがあります。
旧財政課長内かんは、公表されている資料の代表例ですね。
この交付税関係資料については、公式には発表されていないものではあるものの、都道府県の市町村担当課の中には、情報共有のためホームページのサーバーに掲載しており、それがGoogle検索でヒットしたりする事例もあります。
このように、この資料、自治体職員であれば入手は容易ですし、研究者や議員など、自治体職員以外であっても入手するルートはあります。


普通交付税予算は、項目ごとにこう見込む!
さて、ここからは実務的な話。
普通交付税の予算を推計するにあたっての積算に登場する要素は、次のとおりです。
普通交付税=
{(個別算定経費+包括算定経費+各種個別費目+公債費・事業費補正)-臨時財政対策債発行可能額}-基準財政収入額
このうち、{中かっこ}で括った部分が基準財政需要額です。
以下、項目ごとに、どのように見込んだらいいか、説明していきます。
個別算定経費
個別算定経費は、費目ごとの基準財政需要額です。この、個別算定経費の見込み方については、
(各自治体の前年度の個別算定経費の総額-事業費補正)×推計参考乗率
というふうに計算するのがセオリーです。
推計参考乗率という言葉は、「指示伸び率」とか「指示伸び」というふうにも言われておりましたが、総務省交付税課が出す資料においては、この「推計参考乗率」という言い方となっています。
要は



「前年度の算定実績に、国が来年度これくらい伸びるだろうという見込みを乗じて試算してくださいね」
という考え方ですね。
【注意】事業費補正算定額を除いて指示伸び率を乗じる
なお、ここで注意しないといけないのは、
こと。
事業費補正は、要は費目に関連した公債費に対する交付税措置額ですが、この事業費補正は、各自治体の公債費の償還状況に大きく左右されるので、国が示す一律の推計にはなじません。
なので、推計参考乗率は、事業費補正以外のところに対してだけ乗じて、事業費補正算定額は、別途推計額を試算する…というようにするのです。
なお、事業費補正算定額は、普通交付税算出資料中、事業費補正の補正係数額の手前に出てきます。この数値を費目ごとに集めて個別算定経費から除いてから、推計乗率を乗じてくださいね。
包括算定経費
包括算定経費は、主に投資的経費や内部管理経費などを「ざくっと」算定する費目です。
包括算定経費には、人口と面積、それぞれを測定単位とする2つの項目がありますが、どちらにも事業費補正が含まれていますので、個別算定経費と同様に事業費補正算定額を除いてから、推計参考乗率を乗じてください。
なお、この指示伸び率については、総務省自治財政局財政課が公表している資料「令和n年度の地方財政の見通し・予算編成上の留意事項等について」にも登場していますので、完全公表情報だと言ってよいでしょう。


各種個別費目
普通交付税の基準財政需要額における費目の中には、各年度の地方財政計画に呼応するような形で、個別の費目が設定されることがあります。
たとえば、令和6年度の基準財政需要額においては、
- 地域の元気創造事業費、人口減少等特別対策事業費
- 地域社会再生事業費
- 地域デジタル社会推進費
- 人口減少等特別対策事業費
の4項目が設定されています。
これらについては、昨年度の算定をベースに、地方財政計画における同費目の伸び率を勘案しながら見込むのが基本となります。
なお、たまに新設の費目が創設される場合がありますが、そういうときは別途総務省交付税課がわかりやすい資料を作って示してくれることが多いので、それを参考に数字を見込むと良いでしょう。
公債費・事業費補正
続いて、公債費と、個別・包括算定経費の積算において、いったん除いて考えた「事業費補正」の積算です。
これら「公債費・事業費補正」は、地方債の公債費に対する交付税措置額ですが、その措置額は、地方債の償還年数や発行額に大きく左右されます。
またその算定方法も、「同意等額を基礎数値にした理論償還ベース」と「実際の償還額を基礎数値にした実償還ベース」とに分かれており、
といっても過言ではない項目です。



地方税だけでなく、地方債もまた、地方交付税と一体の事務なのにゃ。
さて、この公債費・事業費補正の見込み方ですが、理論償還部分については、算定対象となる各年度の同意等額に、総務省交付税課から毎年示される、理論償還算入係数を乗じて算定額を試算。
また、実償還項目については、令和n年度の償還額に、需要額算入率を乗じて試算。
これらの積み上げを、費目ごとに行っていき、その合計値を「公債費・事業費補正」の需要額として加算します。


臨時財政対策債発行可能額
続いて、臨時財政対策債の発行可能額です。この臨時財政対策債の発行可能額は、基準財政需要額を減少させる項目にもなるので、まずはこの発行可能額を、しっかり見積もります。
令和7年度は地方財政計画において臨財債がゼロになっているので、この作業は不要ですが、いつまた復活するか分からないので、一応書いておきますね。
この臨時財政対策債についても、詳細はかなり細かな積算の資料が総務省交付税課から示されているので、そちらをご覧いただければと思うのですが、基本的には地方財政計画における臨時財政対策債の総額を勘案して見込むのが定石です。
なお、臨時財政対策債発行可能額は、この金額が基準財政需要額から減算され、普通交付税を減方向へと働かせますが、一方で、同額を歳入「地方債」の項目において「臨時財政対策債」として計上することが可能です。
最近は臨時財政対策債を発行可能額全額借りない自治体も増えていますが、年度当初の不測の事態に備え、予算上は全額を計上するとともに地方債限度額の議決を得ておき、もし不用そうなら執行ベースで調整する方が無難だと言えるでしょう。
基準財政収入額
さあ、ここまで、基準財政需要額の積み上げをしてきましたが、今度は基準財政収入額の試算です。
基準財政収入額も、税目ごとに各年度の数値を試算していくわけですが、ここで注意すべきことは、
基準財政収入額も、地方財政計画に連動した形で見込む必要がある
ことです。
普通交付税の基準財政需要額も基準財政収入額も、基本的には地方財政計画の考え方を個別団体ベースに落とし込むように算定がなされます。
なので、基準財政需要額がそうであったように、基準財政収入額も基本的にはそのような形がとられます。
具体的にどのような数値を用いるかについては、地方消費税(交付金)や、法人住民税法人税割や法人事業税(交付金)など、特に影響の大きい項目は総務省交付税課資料で具体的な数値(指示伸び率)が示されており、これらを参考に数値を見積もるとよいでしょう。
なので、
個別自治体の実際の道府県税・市町村税の予算額をそのまま基準財政収入額にトレースすると、地財計画と乖離して、予算を大きく外す可能性
があります。くれぐれもご注意くださいね!
なお、市町村税の固定資産税については、実算定においても当該年度の実際の課税状況を基礎数値にするので、例外的に実課税額を使っても大丈夫な項目です。
固定資産税は安定税目なので、地方財政計画と実際の決算額があまり乖離しないですしね。
まとめ
以上、今回は、普通交付税・臨時財政対策債の予算の見積もり方法について、解説させていただきましたが、いかがだったでしょうか。
普通交付税を構成する、基準財政需要額と基準財政収入額と、臨時財政対策債発行可能額。これらについて、総務省交付税課から示された資料と、各団体の前年度算定結果を突き合わせながら、一つ一つ項目を精査し、数値を積み上げていく…
なかなか大変な作業ですし、普通交付税の制度を正しく理解していないと、この作業が何を意味しているかも見出しにくいところですが、逆に言うと、制度をしっかりと理解すれば、一つ一つの作業が何をしようとしているか、一気に頭に入ってきます。
交付税予算の推計、単なる作業に終わらせることなく、ぜひ交付税の、そして地方財政制度の理解を深めるきっかけにしてみてくださいね!