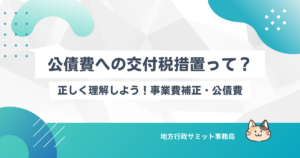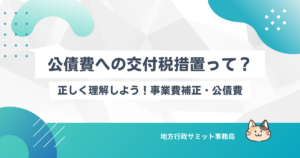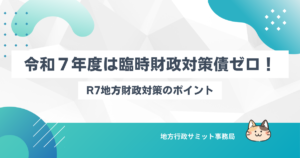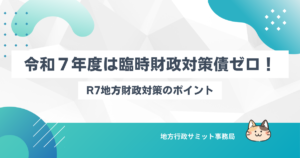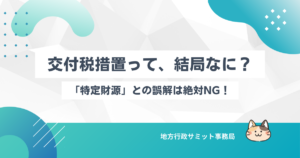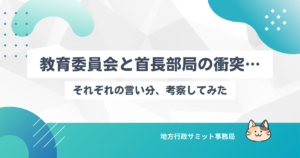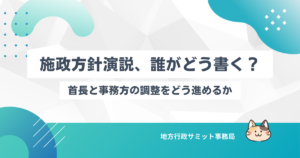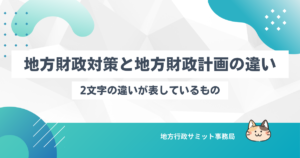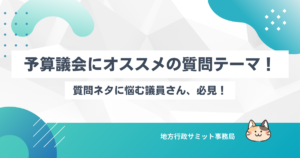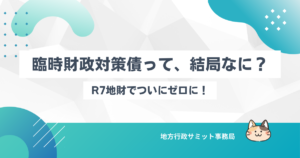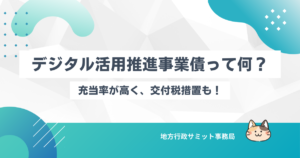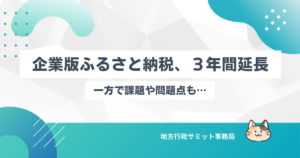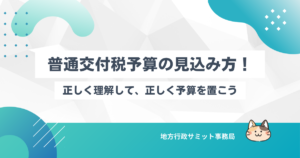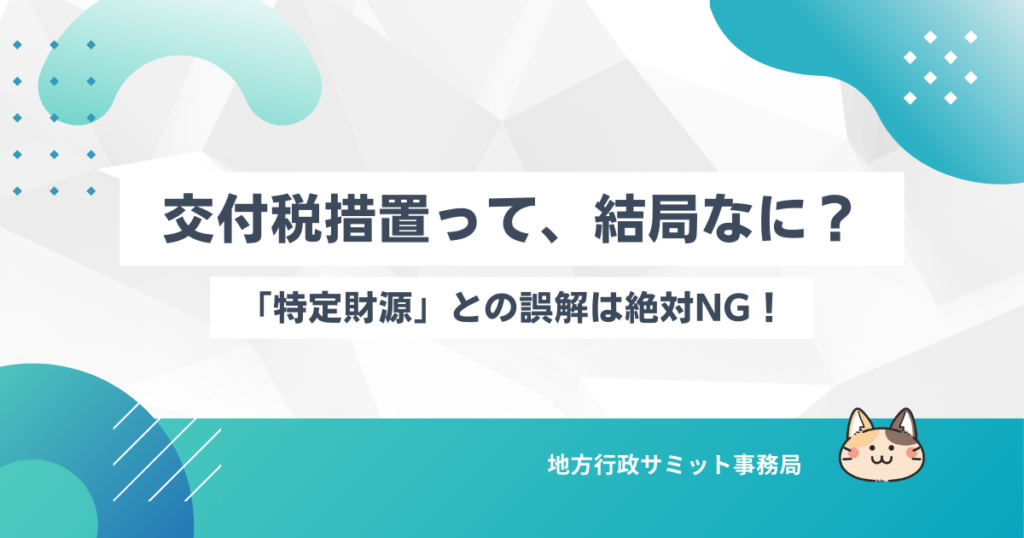
【この記事で分かること】
- 交付税措置とはそもそも何か
- 普通交付税措置と特別交付税措置の違い
- 「交付税措置=特定財源ではない」という話
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、「交付税措置」というものについて取り上げ、その概論をお話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子「交付税措置」を正しく理解できていない人が国・地方ともに多いから、我々が正しい知識の啓発活動を行うのにゃ。
「交付税措置」とは
国の資料などを見ていると、よく見かけるのが「交付税措置」という言葉。
◎◎事業について、総額4,000億円の交付税措置を講じる
みたいな文章、国の各府省が地方向けに出す文書やポンチ絵などに、よく書かれています。
一見、国が何らかの形で地方に財政措置を講じてくれているように見えるのですが…
でも、
「交付税措置」という言葉だと、これがいったいどういうことなのか、財政課経験者以外には、ほとんど分からない
のが実情です。
交付税措置にはいくつかのパターンがある
そこで、この「交付税措置」について説明するのが本稿の趣旨ですが…
実は、この交付税措置には、いくつかのパターンがあります。
それが、
- 普通交付税措置
- 特別交付税措置
この2つです。
交付税制度について少し勉強した方なら、地方交付税には「普通交付税」「特別交付税」の2種類が存在することがご存じのことでしょう。
「交付税措置」には、この「普通交付税」で措置するか、「特別交付税」で措置するかの2パターンがあるのです。
普通交付税措置=基準財政需要額に算入する
ではまず、普通交付税措置について。
普通交付税措置とは、普通交付税の算定に用いる基準財政需要額の中に、対象となる項目の経費を含めて算入すること
を意味します。
普通交付税は、ざっくりというと、
普通交付税=基準財政需要額(標準的な行政経費の一定割合)−基準財政収入額(標準的な税収入等の一定割合)
という算式で計算されます。
以下は、総務省ホームページに掲載されている「普通交付税の仕組み」の図です。
この「標準的な行政経費の一定割合」と呼ばれる「基準財政需要額」の中に、対象となる項目にかかる経費を含めるようにしたものが、「普通交付税措置」と言われるものです。
基準財政需要額は、自治体の予算のように、細やかな費目が定められているのですが、該当案件にふさわしい費目の中で、当該項目について算定する、というわけなのですね。
特別交付税措置=特別交付税の算定に組み入れる
続いて、特別交付税措置についてですが、こちらは、
特別交付税の算定の中に、当該案件にかかる経費を組み入れる
というものです。
特別交付税は、普通交付税の基準財政需要額のように、「基準財政収入額をさっ引く」というような計算式はとっておらず、シンプルに所要額を積み上げる形をとっています。
たとえば、市町村分のJETプログラムコーディネーターに要する経費というものを例にしてみましょう。
これでいくと、「特別交付税に関する省令」第3条第1項第3号(市町村分の12月算定)において、
64 語学指導等を行う外国青年招致事業に要する経費があること。
JETプログラムコーディネーターの活用に要する経費として総務大臣が調査した額に〇・五を乗じて得た額とする。
という規定があります。
これは「総務大臣が調査した額」…すなわち、総務省が自治体に照会して回答のあった数値に0.5を乗じた額が、特別交付税の算定に入るということになります。
ただし、特別交付税は、地方交付税総額の6%と定められていますが、
地方全体で特別交付税の算定に入る数値を積み上げると、特別交付税総額をはるかに上回る数値となっており、特交が足りない
という状況に陥っているのが通例です。
なので、この省令に定められた算定方法を鵜呑みにして、財源がついてくると考えない方が良いでしょう。
原課にいたとき、特交の照会に回答したけど、財政課から「算定額はそれよりはるかに少ないよ」と説明を受けました…
【注意】交付税措置=特定財源がついている、ではない!
ところで、交付税措置については、普通交付税にしても特別交付税にしても、
という見え方をしてしまいます。
従って、これを見た自治体の事業課の担当者が、



交付税は特定財源だ!特定財源つきだから、財政課も簡単に予算をつけてくれるはずだ!
という誤解をしてしまうことが、よくあります。
交付税措置を誤解させがちな事業と府省
特に、
- 学校図書館図書(文部科学省)
- 教材費(文部科学省)
- 予防接種(厚生労働省)
- 妊婦健診、新生児聴覚検査費(こども家庭庁)
あたりは、何なら各府省が意図的に特定財源であるかのように錯覚させるような文書や資料を地方団体向けに発出していたりするから、非常にタチが悪いです。
これは国の中でも、「分かってわざとやってる人」と「ホントに特定財源だと勘違いしてしまっている人」の両方がいると聞きました。
言うまでもありませんが、地方交付税は、地方固有の財源であり、一般財源です。
確かに、その算式には、国における一定の考え方が入っているのは事実ですが、かといって地方団体の財源の使途がそれに縛られるものでは、全くありません。
要求側も査定側も、交付税措置を正しく理解しよう
事業課としては、事業に必要な予算を獲得するための方便として、この交付税措置を特定財源であるかのように財政課や企画課にプレゼンすることもあるでしょうが…
そうした査定担当者側は、「地方交付税が一般財源である」ことを、勉強してよく分かっています。
なので、交付税を特定財源であるかのような説明をすると、



ああ、事業課も同じ地方公務員なのに、全然地方財政制度のことを勉強してないんだな
と、心証を損ねて、かえって査定が厳しくなるだけです。
くれぐれも、交付税を特定財源であるかのように理解するのはやめましょう。
そして、国の各府省も、地方自治体に対して、そういった誤解を招くような資料を発出することは慎むべきだと言うことを、僭越ながら指摘させていただきたいと思います。
もっとも、ここ数年の間に担当になった自治体の政策・財政担当者は勉強不足が著しく、査定する側が交付税措置のことをちゃんと分かっていないこと…という話もよく聞きます。
多くの自治体が財政運営に困らなくなったから、企画や財政部門ですら、まともに財政を勉強していない職員が増えちゃってるみたいだね…。



課長級すらろくに地方財政制度を勉強せず、精神論とかで査定をしてたりすることが多いと聞くから困ったものにゃ…。
なお、密度補正される普通交付税措置や、事業費補正・公債費の算定は、普通交付税を純増させる効果があるので、全部が全部「交付税措置は意味がない」というふうに理解するのも暴論です。
そのあたり、下の記事でしっかり語ってるので、合わせてぜひ見てもらいたいね。
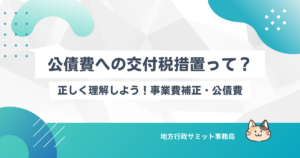
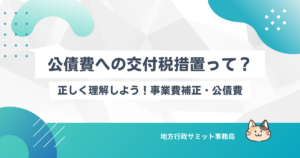
まとめ
以上、本日は、「交付税措置」について、総論的にお話しいたしましたが、いかがだったでしょうか。
交付税措置には、「普通交付税措置」と「特別交付税措置」というものの2つがあり、算定の考え方・措置の考え方は、それぞれ異なっています。
ただし、どちらも地方固有の一般財源であることは変わりなく、
この交付税措置を、あたかも国庫補助金であったり特定財源であったりのように取り扱うことは、交付税制度の理解としては不適切
です。
ただし、この交付税措置を獲得することは、国の各府省にとっては地方が思う以上にハードルが高かったりするのも、また事実。
交付税制度を軸にした地方財政制度の話は非常に奥が深く、さまざまな論点があります。それらも追ってお話ししようと思いますので、乞うご期待!