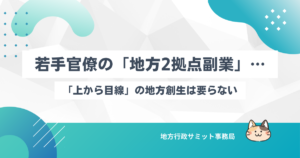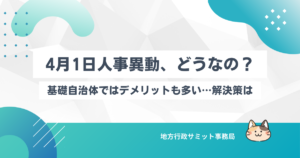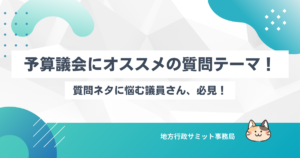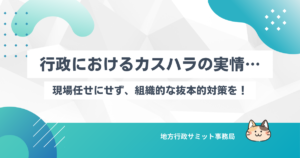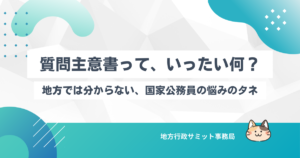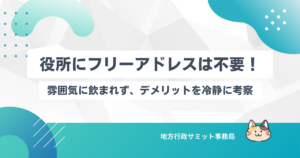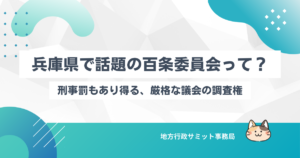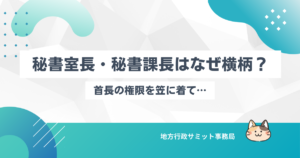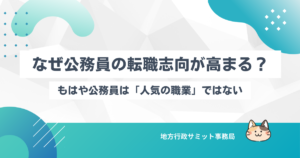【この記事で分かること】
- 「若手官僚の副業2拠点伴走」とは
- 「若手官僚の副業2拠点伴走」の国から見た問題点
- 「若手官僚の副業2拠点伴走」の地方から見た問題点
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、現在国が地方創生の取組の一環として検討している「若手官僚の副業2拠点伴走」について、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子これ、はっきり言って、なかなか筋悪な案件だと思うのにゃ…。
「若手官僚の副業2拠点伴走」とは
現在、国において、「国家公務員が東京と地方の2拠点で活動する制度」というものの検討を始めているそうです。
制度の全容は現時点では明らかにされていませんが、報道等の情報を総合すると、
- 制度の対象は若手の官僚
- 「副業」として担当する自治体に出向き、地方創生の取組の助言を行う
- 自治体の人手不足と官僚の現場体験不足を同時に解決する
というしくみのようです。


なぜ「官僚の2拠点伴走」は不要なのか
しかし、このしくみは、私ははっきり言って悪手であり、現場や当事者の思いが全く入っていないと思われます。
もっとはっきり言えば、この制度は
若手官僚にとっても地方にとっても不要なものであり、即刻具体化を凍結すべき
です。


以下、その理由を述べます。
【理由①】そもそも若手官僚に「副業」する余力はない
この制度は、「若手官僚が副業的に2拠点生活を送り、地方でも働く」ということで、若手官僚が自分の時間の一部を切り出して、地方に捧げることを求めています。
しかし、現実問題として、若手官僚にそのような時間があるのでしょうか。
わざわざ「副業的に」ということは、おそらく「勤務時間外に」ということになるのでしょうが、霞が関で働く国家公務員は、所属府省や事務分担によるとはいえ、基本的に労働時間が長く、超過勤務時間を除いた「勤務時間外」の自由時間というのは、基本的にあまりありません。
府省だと、特に財務、総務(旧自治)、METI、厚労、こ家庁あたりは厳しいかな…
個人的には、厚労・こ家庁の若手官僚には、ぜひ福祉の現場を見てほしいですけどね。
ましてや、仮に勤務時間中の取組が認められたとしても、霞が関は国会対応や予算・法令関係の業務で常時忙しく、とても副業の余裕があるとは思えません。特に、将来を渇望された若手官僚であれば、なおのこと激務の部署で職務に励んでいることでしょう。
そのような若手官僚に「副業的に地方で働け」といっても、本音では



「そんな暇があったら、少しでも睡眠時間をくれ」



「自分の時間がほしいよ…」
となるのが目に見えています。


【理由②】「国>地方」の主従関係が見える
今回の取組は、
という立て付けになっていますが、これはかみ砕いて言うと、
「国家公務員は地方創生のプロなので、地方自治体に地方創生のことを教えてあげる」
ということでもあります。
ここから見えるのは何かというと、
「国が上で、地方が下だという、昔ながらの主従関係」
です。
平成11年の地方分権一括法において「国と地方は対等な関係」との考え方が示され、それから実に25年もの月日が経過したわけですが、それにもかかわらず、このような
- 「国が地方に出向いて助言する」ということ、
- それも本来地方自治体の本務である「地方創生」という業務において、ということ
- 百歩譲って、国が送ってくるのが経験豊富なベテランならいざ知らず、若手の官僚を送ってくること
という点において、国は地方を下に見ているという「本音」が、事実上明らかになっています。
地方分権一括法も所管する内閣府が、このような「国と地方の対等な関係」を否定するスキームを作ることに、何の違和感も覚えないのであれば、それは非常に残念なことだと思います。



国が地方を下に見ているのは、本来地方自治体の味方であるはずの総務省(旧自治)でも感じるときがあるのにゃ…。


【理由③】地方に必要なのはアドバイザーではなく実務担当者
今、地方自治体はかつてないほどの人手不足により、基本的な行政サービスの維持にすら苦労している状況です。
そうした中、システム標準化や税制改正、地方自治体DXの推進など、国策として進められるさまざまな取組にかかる業務量が、一方的に国から付加され、地方自治体の現場で実務を担う担当者たちは悲鳴を上げています。
デジタル化関係はR7地財で財政措置が講じられましたが、そもそもの人手不足の話は解決していないですからね…。
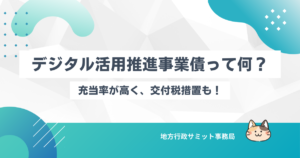
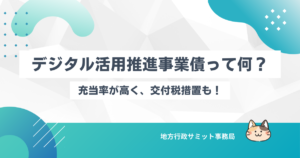
内閣府は、地方創生臨時交付金を活用していない団体が相当程度あることに課題意識を感じており、その背景に「マンパワー不足」を課題として挙げているようですが、そのマンパワー不足を招く背景の一つが、国から一方的に押し付けられる業務負荷です。
なので、マンパワー不足を何とかするには、まずは余計な業務が国から降ってこないようにするのが第一です。この点は強く指摘しておきたいと思います。
また、百歩譲って「国家公務員の2拠点伴走」でマンパワー不足の解決を…というのであれば、
その官僚に求められるのは「幹部補佐としての、上から目線の助言」ではなく、「実際に地域再生計画や交付金の申請書類を作ってくれる実務作業」
であることも、合わせて指摘いたします。
まとめ
以上、本日は国において検討されている「若手官僚の副業的な2拠点伴走」について、批判的に論じさせていただきました。
石破総理になって、地方創生の取組に力が入る国の方針というものは一定理解しますし、地方が元気になることが国全体の底上げになることも、私は賛成です。
ただ、その手段として、「若手官僚が副業的に2拠点伴走を行う」というのは、どう考えてもその政策目的に沿ったものだとは思えません。
若手官僚がそもそも多忙な上、国が地方を下に見ていることも本制度では露骨に明らかですし、地方の現場が必要としているのは助言者ではなく実務担当者なのが現実だったりするし…。
この制度、おそらく、内閣府の官僚たちが、霞が関・永田町の中で既存スキームを参考にしながら作ったのでしょう。
しかし、そういったスキームには、地方自治体の現場には全く必要がなく、むしろ地方からは
「また国が地方の実情を何にも分かっていない制度を作ってきた」
とため息がもれるばかり。
そして、この制度の活用実績がおそらく内閣府で何らかの指標になるであろうことから、実績づくりのために強力なプッシュが行われることになり、ますます地方の負担が増えることになってしまうのは、目に見えています。
地方創生の取組に反対する地方自治体はいません。
だからこそ、具体的にどういう取組をするかは、丁寧に地方とコミュニケーションを取りながら「本当に役に立つスキーム」を作り出してほしいと、改めて思わずにはいられないのです。