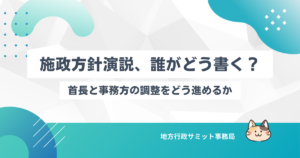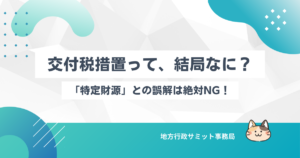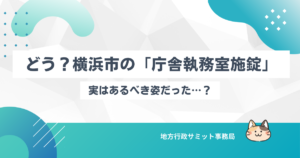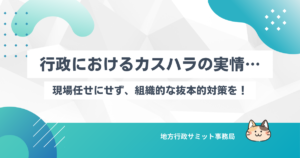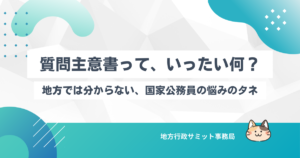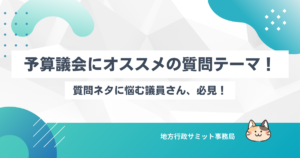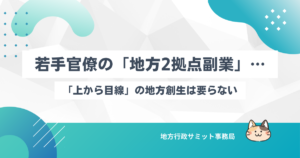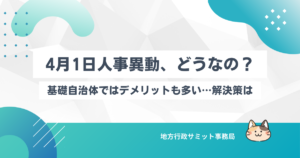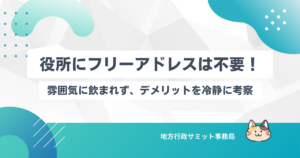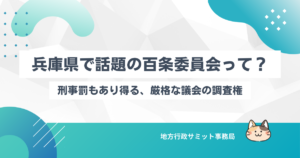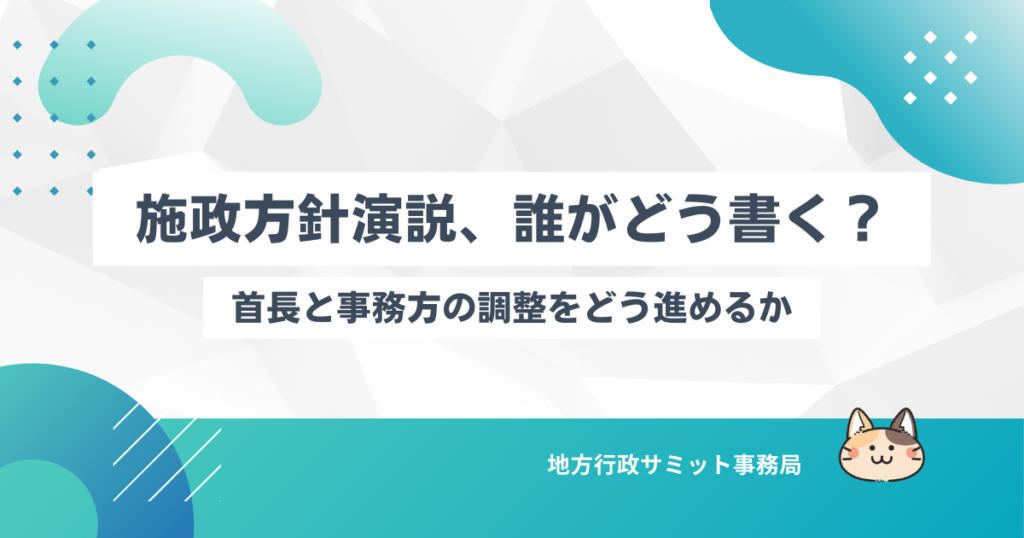
【この記事で分かること】
- 施政方針演説とはそもそも何か
- 事務方はどのように施政方針演説を作成するのか
- 施政方針演説に政治的メッセージを込めるときはどう調整するか
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、地方自治体における施政方針演説について、取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子施政方針演説を誰がどう書くかは、結構自治体や首長の個性が出る、興味深い論点なのにゃ。
そもそも施政方針演説とは
施政方針演説というと、地方自治体にかかわりのない多くの人は、ニュースで内閣総理大臣が行うものを一般的に想起します。
もので、通常国会の冒頭で行われます。
この内閣総理大臣の施政方針演説に続いて、
- 外務大臣の外交演説
- 財務大臣の財政演説
- 経済財政政策担当大臣の経済演説
が行われ、後日各会派1名がこれらの演説に対して代表質問を行う、という流れになるのが慣例です。
地方自治体でも行われる施政方針演説
そして、地方自治体でもこれとおおむね同様の流れがとられており、通常、予算議会の冒頭に、首長が1年間の自治体運営の基本的な方針や政策、予算について説明を行う施政方針演説が行われているのです。
地方自治体における予算議会は、主に来年度予算を中心に審議することになるため、
施政方針演説は、当初予算案の提案理由説明といった色合いが強くなる
のが通例となっています。
また、施政方針演説ののちに、地方自治体議会においても代表質問・代表質疑が行われることが一般的です。


施政方針演説は誰が書くか
さて、この施政方針演説の原稿ですが、誰が書くかについては、いくつかのパターンがあります。それぞれ、メリット・デメリットがありますので、これらを見ていきましょう。
【パターン①】首長が直々に執筆
職員や国家公務員、あるいは地方議会議員からの転身組など、自治体実務を経験した首長の就任直後だったりすると、首長が自ら執筆するパターンがあります。
この場合、事務方はすべて首長にお任せしておけるから楽…となりそうなものですが、実際はそんなに甘くありません。
政治家が自らの思いで作り上げた原稿は、事務的に推敲すると修正が必要になるパターンも多く、実はこの修正プロセスが結構手間だったりします。
というのは、事務方にとっては神経を使うもの。
あまり事務的な修正ばかりを連発すると、首長から



「政治家の原稿につまんない修正ばかりしやがって!」
と怒られるのでは…と不安になりますし、かといって出てきた原稿をそのまま追認してしまうと、あとで議会で質問されたとき、事務レベルでは対応できなくなる恐れもあるし…
と、実はこの「首長自らパターン」、決して楽ではないのが現実です。
「文句ばっかり言うんだったら、自分で書いたらいいのに」と言うのは演説執筆者の定番文句ですが、実際に自分で書かれると、これはこれで困るんですよ…。
【パターン②】秘書or企画課長と首長で執筆
先述のパターンのように、首長だけで原案を作り上げられてしまうと、その修正プロセスが大変になってしまうので、そこに秘書課長または企画課長を入れる、というパターンも聞きます。
この場合、首長が原案を作るパターンもありますが、多くの場合、秘書or企画課長が原案を書き、首長と2人で議論をして、原稿を練り上げていくパターンの方が多いでしょう。
このパターンは
- 意思形成にかかわる人間が絞られるので、一貫性のある文章が作れる
- 首長の関与の度合いも強いので、政治的なメッセージも保たれる
- 一方で事務方も一定関与しているので、事務的な押さえも可能
といったメリットがありますが、一方で秘書or企画課長という中枢部門の課長が、事務的な作業にかなり手を取られてしまうので、組織マネジメント的には必ずしも良い手法だとは言えないかもしれません。
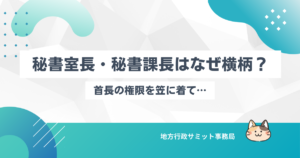
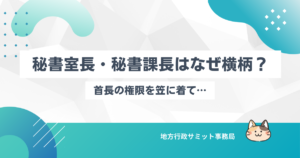


【パターン③】担当者が執筆し、決裁ラインで修文
企画担当課に施政方針演説の執筆担当者を置き、その職員が原文を作成して、首長までの決裁ラインで修文を繰り返しながら、文章を練り上げていくパターンです。
ある意味、もっとも「役所らしい意思形成手法」だと言えるでしょう。
このパターンの場合、ボトムアップで文章を作っていくことになりますので、事務的な押さえは一番しっかりとできるのですが…
一方で意思決定にかかわる人が多すぎるため、文章に一貫性がなくなったり、また事務方ばかりが調整にかかわるため、政治的なメッセージが込めにくかったり、といった課題も生じます。
首長が政治家としてのパフォーマンスを求めない場合であれば、この手法が一番手堅く施政方針演説の原稿を仕上げることができますが、首長が政治家として強いメッセージを発したいタイプの人だったりする場合、この手法だとなかなかゴールにたどりつけません。
とはいえ、このパターンの場合、冒頭あいさつや最後の締めの部分だけを首長自身が書くことで、一定の政治的なメッセージを込めることは可能です。
いくら企画担当課とはいえ、担当レベルで首長に成り代わって政治家としてのメッセージを書くことは難しいでしょうから、可能であれば一部を首長自身で書いてみるよう進言するのも一手でしょう。
最後の仕上げを首長が引き取ってくれたら、担当者はだいぶ楽になりますね。



とはいえ、たまにエキセントリックな謎文章を突っ込んでくる首長もいるから、事務方チェックは欠かせないのにゃ。
重大なメッセージが含まれる施政方針演説は幹部マターに
ところで、この施政方針演説は、首長が政治的にメッセージを発する場でもあることから、時として、首長が非常に重いメッセージを載せることがあります。
特に多いのが、
「今後の身の処し方」
です。
任期満了が近いときは、次の選挙に立候補するのか。あるいは、別の自治体や国政へ転身するのか。
こういった、政治的に重要なメッセージを、施政方針演説の中で述べることがあります。
これ、事務方が一番困るやつです…。
施政方針演説は、議会に対して行うものなので、施政方針演説の中で自らの今後について説明することは、議会に対する首長としての説明責任をしっかり果たすことにもつながります。
一方、こういった政治的なメッセージについては、議会より先に一般に広まってしまうと大問題になってしまいます。
ですので、仮にこういった内容が施政方針演説に含まれる場合、たとえ【パターン③】の事務方主導事例においても、途中で担当者から引き揚げられ、幹部マターとなることが一般的です。
施政方針演説には、こういった要素もあるので、たとえ結果として政治的なメッセージが含まれていなくても、その取扱いには慎重さが求められるものになるのです。
まとめ
以上、本日は、施政方針演説について、そもそものお話から立ち返りつつ、事務的にはどのような手法で調整していくかを見ていきましたが、いかがでしたでしょうか。
施政方針演説は、首長が自らの大きな方針を議会に対して語るという、非常に重要なスピーチ。
それゆえに、その調整にはかなりの手間と時間がかかりますが、そのプロセスをどのように進めていくかについては、首長の個性や自治体組織のありようになどによって、いくつかのパターンがあります。
ただ、いずれのパターンであっても、施政方針演説の重要性は変わりません。
ときとして政治家の今後や政治生命にさえ言及していく、施政方針演説。
こういった内容を事務方として触れることについて、恐れ多さのようなものを感じることもありますが、逆に言うと政治家にお仕えする事務方としては、非常に貴重なチャンスであることは間違いありません。