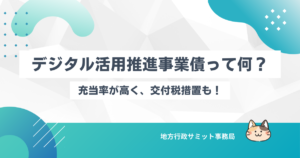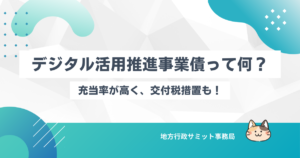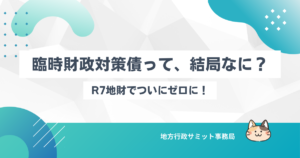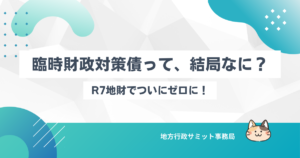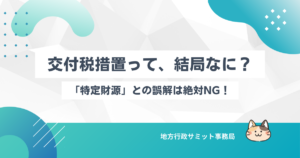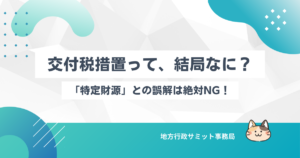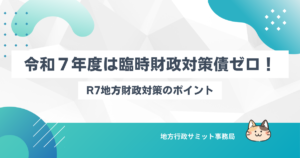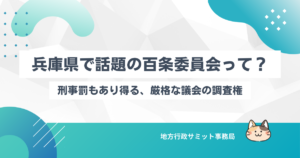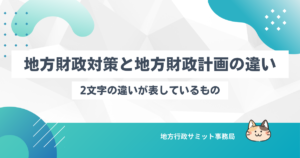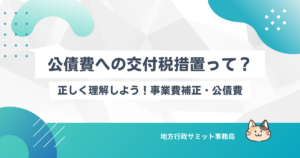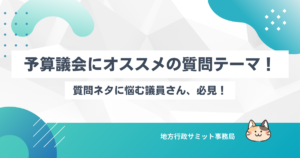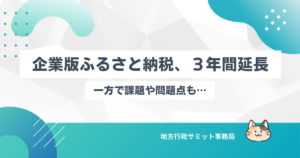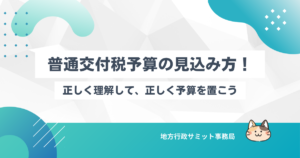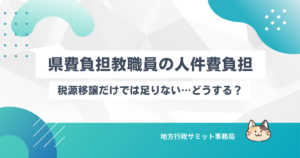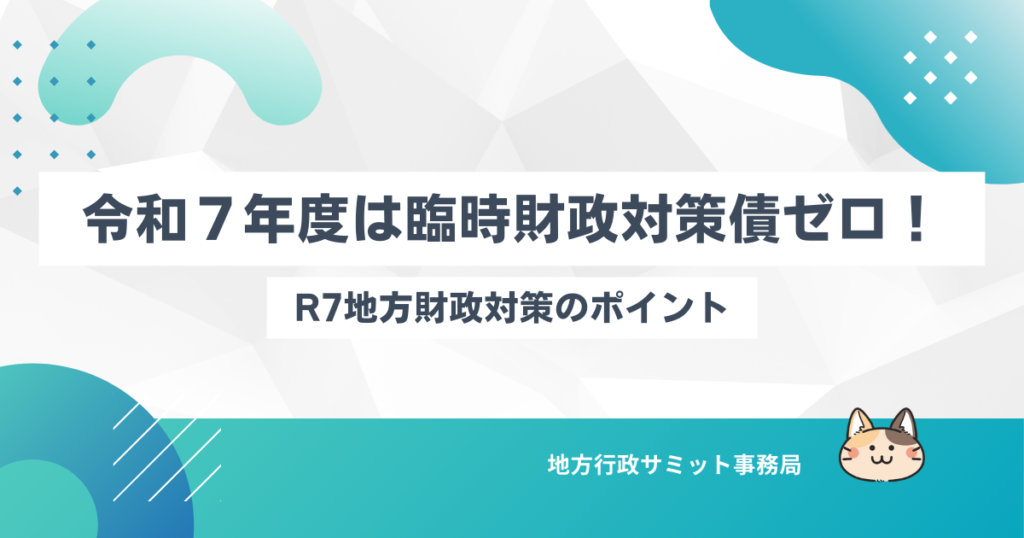
【この記事で分かること】
- 令和7年度地方財政計画・地方財政対策の方向性
- 総務大臣・財務大臣折衝のポイント
- 令和7年度は臨時財政対策債がゼロに
- 「103万の壁」にかかる令和7年度地方財政への影響
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、令和7年度地方財政対策に向けた大臣折衝と、これを受けて公表された令和7年度地方財政対策について取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子特に今回「臨時財政対策債の新規発行なし」という象徴的な出来事があったのにゃ。
総務大臣と財務大臣の予算折衝
地方公共団体にとって、地方税と並ぶ歳入の根幹になるのが、地方交付税。
この地方交付税は、国税の一定割合などから成るもので、総務省としては「地方固有の一般財源だ」と主張してはいるものの、国の立場としては「地方向け交付金の一部」となっており、財務省の予算査定を経ないと決まりません。
その査定におけるチェックポイントが「地方財政計画(地方財政対策)」。この地方財政計画において、地方の歳出総額を見込み、これに対応できる財源を保障するために、地方交付税総額を決めるのです。
地方交付税の予算査定は、総務省自治財政局財政課が財務省主計局の地方財政係に対して行い、主に財政課の財政企画官と財務省主計局の主査がやりとりをする中で進んでいきますが、査定が進む中で少しずつステージが進んでいき、最終的には
総務大臣と財務大臣による、直接の予算折衝
が行われることになります。
この「大臣折衝」が行われると、いよいよ地方財政対策を決める作業も大詰め、といったところです。
もちろん、他府省でも、予算にかかる大臣折衝は行われているよ。


令和7年度地方財政対策のポイント
そして、この大臣折衝を経て、地方財政対策の方向性が決まり、年の瀬となる12月27日、令和7年度地方財政対策が公表されました。
この地方財政対策に基づいて、国の地方交付税(地方交付税交付金)の予算額が決まり、それらも含めた政府予算案が確定するわけです。
なお、政府予算のうち、地方負担を伴うものについては、その地方負担部分が地方財政計画に反映されることになっています。
このあたりは別記事で詳しく説明したいところだね。
それでは、令和7年度の地方財政対策、どのような話になったのか、早速見ていきましょう。



iJAMPよりも早く、そしてiJAMPよりも詳しい地方財政対策の速報解説記事を目指すにゃ!
【ポイント①】一般財源総額は「交付団体ベース」で+1.1兆円
地方公共団体の一般財源総額は、実はこの地方財政対策における「交付団体ベースの一般財源総額」の動きで余裕度が決まってきます。
令和7年度については、「交付団体ベースで1.1兆円増額」ということが示されていますが、これはどういうことかというと、
税収が伸びたことによって不交付団体だけが潤うのではなく、交付税の増を通じて交付団体ベースに一般財源総額の増が行き届く
という意味。
地方財政計画は、地方公共団体の総体としての数値が集計されていますが、財政運営の考え方は、交付税に依存しない不交付団体と、交付税も含めて一般財源総額が確保されている交付団体とでは大きく異なります。
税収増局面においては、不交付団体は税収増がそのまま一般財源総額の増になりますが、一方で交付団体は普通交付税の算定によってその効果は減衰し、一般財源総額ベースにはあまり影響が出ません。
一方、今回の地方財政対策のように「交付団体ベースで1.1兆円の税収増」というものが示されると、「不交付団体以外の団体にも一般財源総額の増効果が得られる」ということを示しているので、ある程度歳入については算段がついた、ということが言えるようになるのです。
なお、新聞記事の見出しとかで「地方交付税総額は前年度を上回る19.0兆円」とかをよく見ますけど、マクロにおける交付税総額の増減なんて、個別自治体の予算編成には全く関係ないから、無視してくださいね!
ちゃんと見ないといけないのは、「一般財源総額」と「地方財政計画の歳出総額」だからね。
【ポイント②】臨時財政対策債がついにゼロに!
今年度の地方財政対策の中で一番大きいトピックスは、これだと思います。
令和7年度地方財政計画において、臨時財政対策債の計上額はゼロ
となったのです。
地方財政計画の歳出総額を埋めるために、さまざまな財源対策を講じたものの、なお埋め切れなかった赤字部分について、地方が借金して賄うのが、臨時財政対策債。
この臨時財政対策債については、後年度の公債費が地方財政計画に全額計上されるとともに、個別自治体の普通交付税算定において、基準財政需要額に100%算入されることとされていますが、この臨時財政対策債の公債費もまた地方財政計画を圧迫しており、長期的な地方財政運営において支障になると目されていました。
一方で、近年の地方財政は税収増の影響もあってきわめて健全な運営が続いていて、臨時財政対策債に依存する部分が少しずつ減少してきていました。
そしてついに令和7年度、臨時財政対策債がなしでも地方財政計画がバランスするほどに、地方財政計画が健全化してきたのです。
平成13年度から始まった臨時財政対策債が、ついにゼロになる…。国・地方問わず、地方財政にかかわってきた関係者にとっては、きっと感慨深いものとなったことでしょう。
とはいえ、過去に発行した臨財債の償還はまだまだ続きますから、決して地方財政がただちに楽になった、というわけではないんですけどね。
交付税特会の借入金も含めると、まだまだ地方名義の借金はたくさんあるんだよね…。
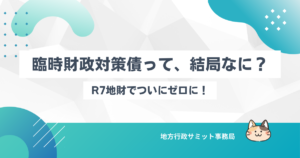
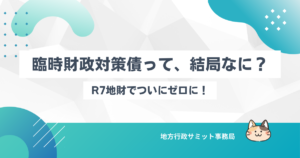
【ポイント③】デジタル活用推進事業債の創設
最近、さまざまな自治体でデジタル化・DXの取組が進められるようになりましたが、これらの取組については、イニシャルコストが大きくかかることがあり、財政状況に余力がない自治体では、なかなか気軽に手を出せない状況にあったのも事実。


そこで、令和7年度地方財政対策において、歳出に「デジタル活用推進事業」を計上するとともに、その財源として「デジタル活用推進事業債」という地方債を創設し、活用できるようにしました。
地方財政法第5条但し書きが定める適債事業というと、どうしても土木・建築などのハード事業を思い浮かべることが多いですが、一方で経費の性質として、デジタル関係のイニシャルコストは意外とこれに近い面もあり、そこに活路を見出して地方債メニューとして追加したのかな…と理解しているのですが、一方でR7地方財政対策のPRペーパーには「地方財政法の特例を設け」と書かれており、どのような理屈で地方債を作ったのかは続報を見ないと分からないところではあります。
地方債メニューの中身としては、
- 充当率:90%
- 交付税措置率:50%(公債費で需要額算定か事業費補正かは不明)
- 償還年限:5年
- 期間:令和11年度までの5年間
- 事業費:1,000億円(うち地方債は900億円)
となっています。
交付税措置50%は、かなり大きいですね…!
具体的な充当対象事業や資金区分などの詳細は、これから整理されることになるのでしょうが、デジタル化の財源に悩んでいる団体にとっては朗報になりそうですね。



ただ、これは予算と関係にゃいが、最近いろんな自治体で「デジタル化・DX担当課と原課のあつれき」みたいな話を聞くようになったにゃ…。
そう!デジタル化は手段であって目的ではないのに、デジタル部門はそれ自体を目的化して現場にDXを強制してくるから、しんどいしやる気もそがれるの!
「DXという手段の目的化」、興味深い論点だから、また別記事で語ってみても良いだろうね。
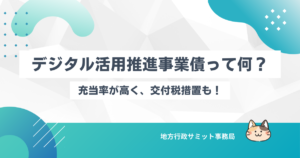
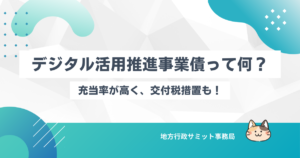
【ポイント④】給与改定に伴う人件費増を地財歳出で措置
今年度の人事院勧告に伴う給与改定で、多くの自治体は人件費水準が上昇しました。
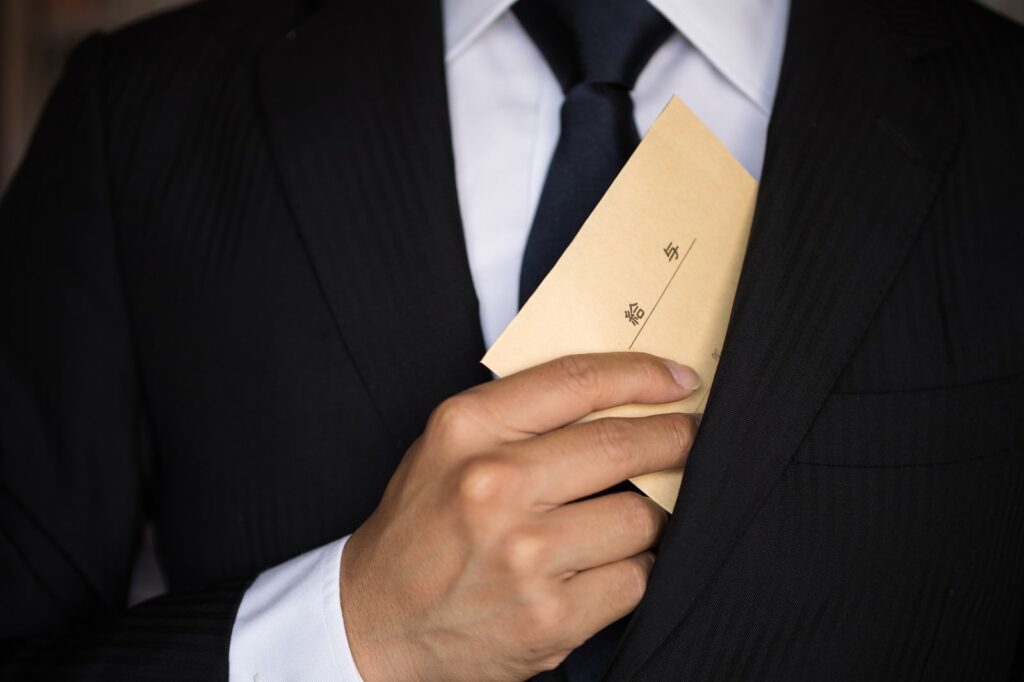
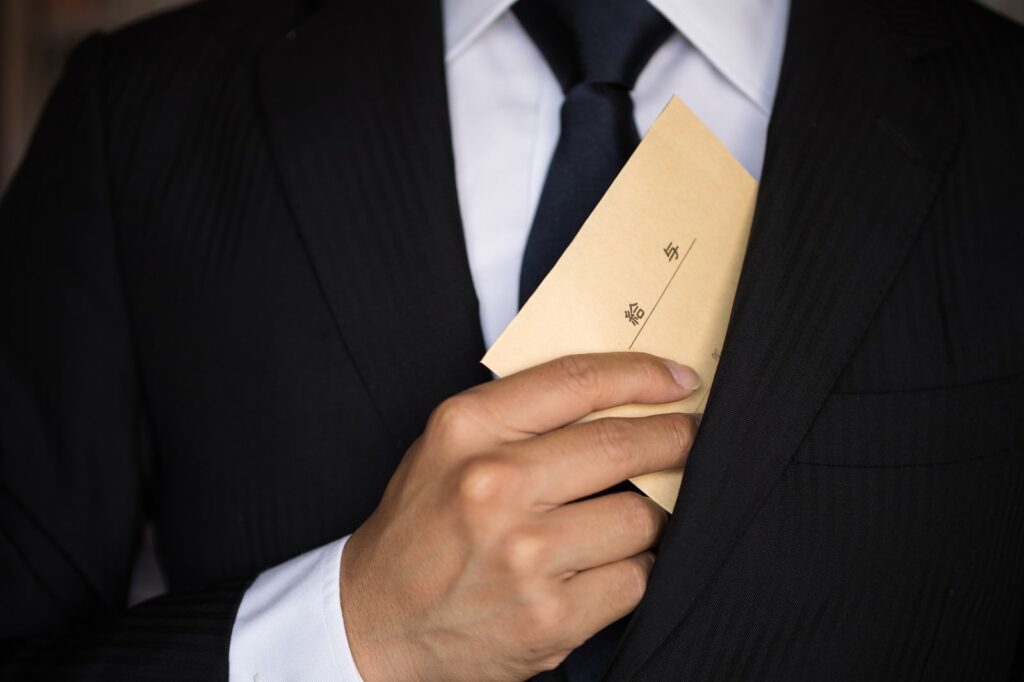
特に改定幅の大きい若手は、突然大金が振り込まれて、大喜びしていましたね。
財政課や給与課は、相当苦労していたけどね…。
この人件費水準の上昇は、財政運営上は非常に重たいダメージとなってのしかかってくるのですが、その財源を地方財政計画の中で保障すべく、令和7年度の地方財政対策において、
- 給与改定や教職調整額の改定に伴う+0.8兆円
- 給与改善費+0.2兆円
が計上されることとなりました。これらは地方財政計画の歳出に積み上がりますので、普通交付税の算定に際して基準財政需要額に反映されることとなります。
ただし、令和7年度は税収増局面にあるので、「留保財源見合いの需要額蹴り出し現象」が発生することはほぼ確実。この場合、基準財政需要額の算定額からは人件費増を読み取れないかもしれません。
この「税収増局面における留保財源見合い需要額の蹴り出し」、マニアックだけど大切な論点だから、これもまた、どこかで記事化しようね。
【ポイント⑤】「103万円の壁」に係る地方財政への影響は微々
令和7年度税制改正において、大きな話題となった「103万円の壁」問題。
これは、最終的に、令和8年から「125万円」に改められることとなりましたが、地方財政を見ている立場としては、これに伴う税収減がどうなるかが、非常に気になるところ。
令和7年度の地方財政における影響としては、地方税(個人住民税)についてはまだ影響が発生しないのですが、一方で地方交付税の原資となる国税は、令和8年1〜3月分がこれの影響を受けることから、交付税法定率分において▲0.2兆円の減収が発生します。
ただし、そもそもの税収自体が非常に好調なので、▲0.2兆円くらいは全体の税収増の中で飲み込むことが十分可能となっており、先ほどの「臨時財政対策債ゼロ」も、この影響があった上でなお達成できているくらいに、今年度の地方財政対策は強力なものになっています。
まとめ
以上、本日は「令和7年度地方財政関係大臣折衝のポイント」についてご説明させていただきました。
地方公共団体の財政運営に、非常に大きな影響を及ぼす地方財政計画・地方財政対策の姿が、この大臣折衝くらいから少しずつ見えてくることになるので、自治体財政課職員にとっては見逃せない情報です。
令和7年度向けの大きなトピックス、改めて整理すると、こんな感じです。
- 一般財源総額は「交付団体ベース」で+1.1兆円
- 臨時財政対策債がついにゼロに!
- デジタル活用推進事業債の創設
- 給与改定に伴う人件費増を地財歳出で措置
- 「103万円の壁」に係る地方財政への影響は微々
この情報を見ながら、ぜひ、各自治体の予算編成を進めていただければ幸いです!