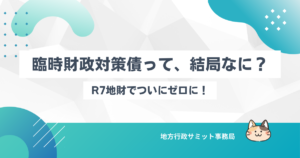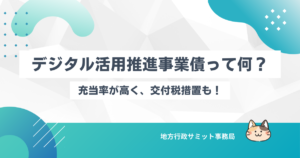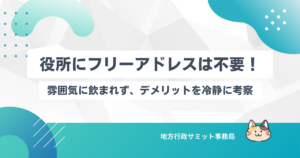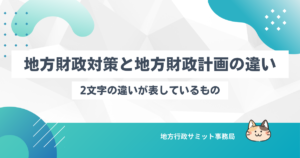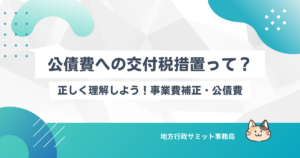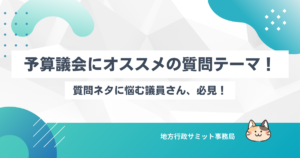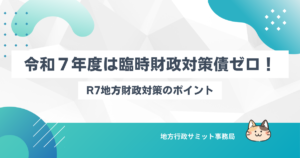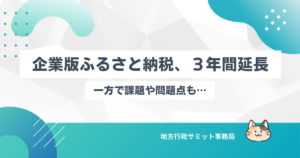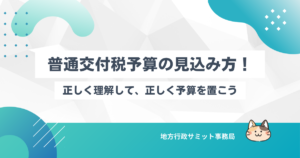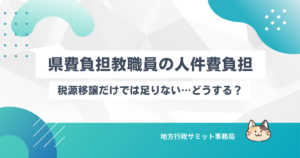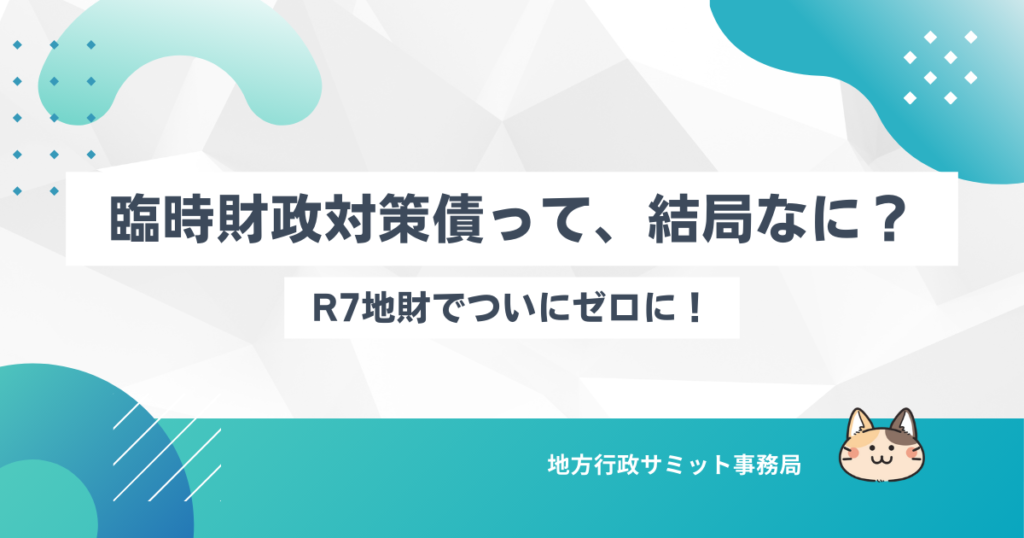
【この記事で分かること】
- そもそも臨時財政対策債とは
- 臨時財政対策債はどのような経緯で誕生したのか
- 令和7年度地財で臨財債がゼロになったのはなぜか
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、令和7年度地方財政対策において、ついにゼロにすることができた臨時財政対策債について、取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子「ゼロになった」という話題ばかりが一人歩きしてるけど、そもそも臨時財政対策債のことをちゃんと知らないままに騒いでいる人も多いのにゃ。
臨時財政対策債のざっくりとした理解
臨時財政対策債。
地方財政にかかわったことのある人なら、一度はこの名前を聞いたことがあるのではないかと思います。
これについては、
- 地方交付税の一部振替措置であり、実質的には地方交付税と同じ
- 後年度の公債費は交付税措置されているから発行しても問題ない
- とはいえ、自分のところの決算統計を見ていると、地方債残高がめちゃ増えてるから、実は心配…
など、さまざまな立場から、いろんな意見や感想が出ています。
そんな臨時財政対策債とは、果たしていったい何なのでしょうか。
臨時財政対策債の辞書的定義
まずは臨時財政対策債について、辞書的な定義を見てみます。
臨時財政対策債
地方公共団体の一般財源不足を補うため、地方財政法(昭和23年法律第109号)の規定に基づき、特別に発行を認められた地方債です。
臨時財政対策債の発行に伴い地方公共団体が将来にわたって支払うべき元利償還金は、後年度の地方交付税としてその全額が措置されることとなっています。
※地方公共団体金融機構ホームページより(https://www.jfm.go.jp/financing/loan/rinji.html)
これだけでは分かったような分からないような話なので、もう少し、詳しく見ていきましょう。
地方財政計画の財源不足
国は、地方交付税法の規定により、毎年度地方財政計画を作って国会に提出するとともに、一般に公表しています。


この地方財政計画において、国は毎年度の地方の一般的な歳出総額を見積もるわけですが、一方でその歳出総額に見合う歳入…すなわち、財源が足りないことがでてきます。
地方財政計画の歳入といえば、主なものは、地方税と地方交付税(法定率分)です。また、このほか、特定財源である国庫支出金や地方債などもあります。
これらの歳入をもってしてもなお、地方財政計画の歳出に見合う歳出を確保できない場合、国は歳出を削るのではなく、歳出に見合う歳入を確保できるよう、さまざまな策を講じます。
地方債充当率のかさ上げ(財源対策債)、交付税特会の余剰金活用、地方公共団体金融機構金利変動準備金の活用…
こういったものが、地方財政計画上の「財源対策」と呼ばれます。
国がこのようにして地方全体の財源を確保するために四苦八苦している様子は、あまり地方に知られていないんだよね。
財源不足が生じたときは「折半ルール」
こういった財源対策を講じても、なお財源不足が生じる場合、
することになっています。
国は、赤字国債を財源にした地方交付税の増額。
そして地方は、臨時財政対策債の発行。
こういった形で、国と地方がそれぞれ借金することで地方財政計画の穴を埋め、地方財政計画の歳出に見合う歳入を確保する。
こうすることで、地方全体が1年間、標準的な行政サービスを提供するための財源が確保されることになるわけです。
なお、臨時財政対策債については、当然地方債なわけですので、後年度に公債費…すなわち借金返しが必要になるのですが、その公債費については、後年度の地方財政計画に所要額が計上されるとともに、各団体の基準財政需要額にも算定されるようになっており、後年度の財源も一応措置されていることになっています。
ちなみに、臨時財政対策債にかかる公債費の基準財政需要額算入は、発行の有無にかかわらずなされます。
過去は「交付税特別会計借入金」で財源補てん
ところで、「臨時財政対策債」というものは、平成13年度から創設された地方債メニューなのですが、平成12年度以前はどうなっていたか。
平成12年度以前も、財源不足が生じたときに、「国と地方で折半して、それぞれが借金してまかなう」という、いわゆる折半ルールはあったのですが、
臨時財政対策債の創設前は、この「地方の借金」を、交付税特別会計で借金し、それを原資に地方交付税を増額して補てん
していたのです。
そして、その交付税特別会計における借金の返済原資は、後年度の地方交付税を減額する形で捻出する…
こういう形で、地方財政計画を組んでいたのです。


「地方負担」意識付けツールとしての「臨財債」
しかしながら、このスキームは、
「交付税特別会計で借金をしている」という事実が、地方団体に伝わりにくいものとなっていた
のが実情です。
また、交付税特別会計は、当然に国の特別会計ですので、実際に借金を返済する事務は、国が行います。よって、特会借入金の返済が直接的に地方団体の財政負担になっているという実感は得にくいもの。
そこで、
「折半ルールによる地方負担は、地方の借金である」ということがより直感的にわかるよう、平成13年度地方財政計画において、「臨時財政対策債」というものが創設
されます。
平成13年度当時の「地方財政計画の概要」を見てみましょう。
○ 従来の地方財政対策を見直し、国と地方の責任分担の更なる明確化、国と地方を通ずる財政の一層の透明化等を図るため、平⑬から平⑮までの間においては、この間に予定されている交付税特別会計借入金の償還を平⑲以降に繰り延べることとしたうえで、なお生ずる財源不足のうち財源対策債等を除いた残余については国と地方が折半し、国負担分については一般会計からの繰入れにより、地方負担分については特例地方債により補てん措置を講じる制度改正を実施
ここにいう「特例地方債」こそが、まさに臨時財政対策債を差しています。
もともとは「臨時」だったが…いつのまにか「経常」に
こうして、平成13年度に臨時財政対策債が創設されたわけですが、当初は平成13〜15年の間の時限措置とされていました。
この「3年間の限定」という思いがあったからこそ、この特例地方債には「臨時財政対策債」という名称がつけられたものと理解しています。
ところが、その後も折半対象財源不足は解消せず、この制度はさらに3年延長。
一時は折半対象財源不足こそなくなったものの、平成20年9月のリーマンショックで再び地方財政計画は折半対象収支不足が生じ、以後、今日に至るまで、臨時財政対策債は継続して地方財政計画に計上され、各地方団体で発行されています。
改めて振り返ると、平成13年度から令和6年度まで、実に20年以上、臨時財政対策債は、発行され続けていることになりますね。
令和7年度地財で、ついに臨財債がゼロに!
このように「臨時」といいながらも、事実上「経常」的な財源として用いられてきた臨時財政対策債。
そんな臨時財政対策債に、令和7年度、大きな転機が訪れます。
令和7年度地方財政対策において、ついに臨時財政対策債の計上額がゼロとなった
のです。
平成13年度の臨時財政対策債創設以降、実に20年以上続いてきた、この赤字地方債でしたが、令和7年度は好調な地方税収、そして法定率分の交付税原資に助けられて、地方全体での財源不足額が大幅に圧縮されました。
しかもこれ、地財の歳出には人件費の増をはじめとしたさまざまな財政需要が乗っかり、地財規模が拡大する中にあっての、財源不足額の圧縮なのです。
こういった状況下における臨時財政対策債の皆減は、地方財政関係者に、非常に大きなインパクトを残しました。
令和8年度以降の臨財債は…「103万の壁」問題次第?
さて、令和7年度地方財政対策が発表された直後にあって、こんな話をするのは気が早いかもしれませんが、



令和8年度地財で、臨財債はどうなりそうかな?
ということが気になる方もいらっしゃることでしょう。
もちろん、現時点で令和8年度の臨財債の話をするのは、気が早すぎて鬼も笑わないレベルかもしれませんが…一応考えてみましょう。
現下の税収好調状況は、おそらく短期間の間に悪化することは通常あまり考えられないでしょうから、おそらく来年度の地方税収や、交付税原資となる国税も一定好調を維持するのではないかと思います。
ただし、注意しなければならないのは、「103万の壁」問題です。
これが令和8年度税制改正で、さらに踏み込んだ改正がなされる場合、地方税収も国税も大きく減少することが見込まれるでしょうから、この税制改正の結果如何によっては、再び臨時財政対策債が発生してしまう可能性も、十分にあるかもしれません。
なので、令和8年度の臨財債がどうなるかは、「103万の壁」の議論を注視しながら、その行方を見守ることで、自ずと見えてくるのではないでしょうか。


まとめ
以上、本日は、令和7年度地財においてついにゼロとなった臨時財政対策債について、これがそもそも何なのかも含めて、過去からしっかり振り返ってみました。
臨時財政対策債については、特に地方自治体の首長や職員において、正確に理解されているとは言いがたい状況にありましたが、この地方債のことを正しく理解することは、マクロの地方財政を正確に理解する上で必要不可欠です。
今回、令和7年度地財においてついにゼロとなりましたが、これがゼロになったというトピックスがあるということは、各自治体の予算議会における議論でも話題になるかもしれません。
そんなときに、いい加減な理解で臨財債を語って恥をかくことがないよう、皆さん、臨財債のこと、しっかり勉強していただければ幸いです!