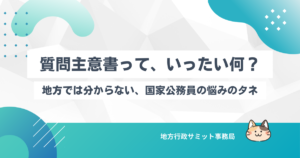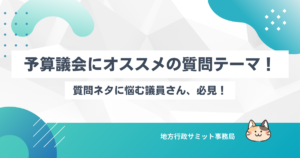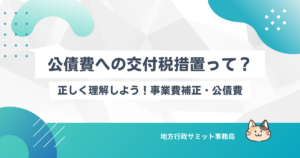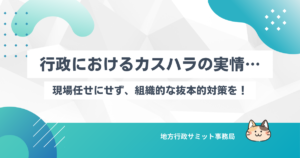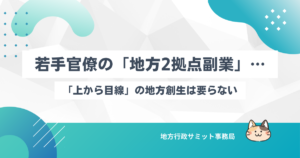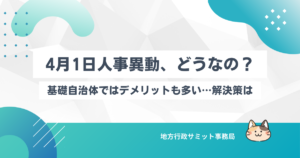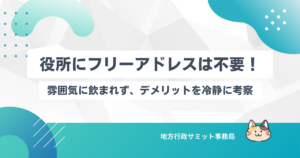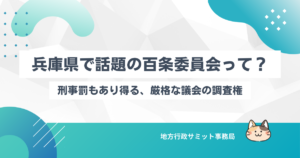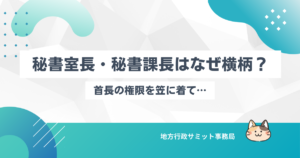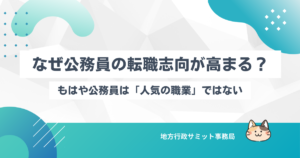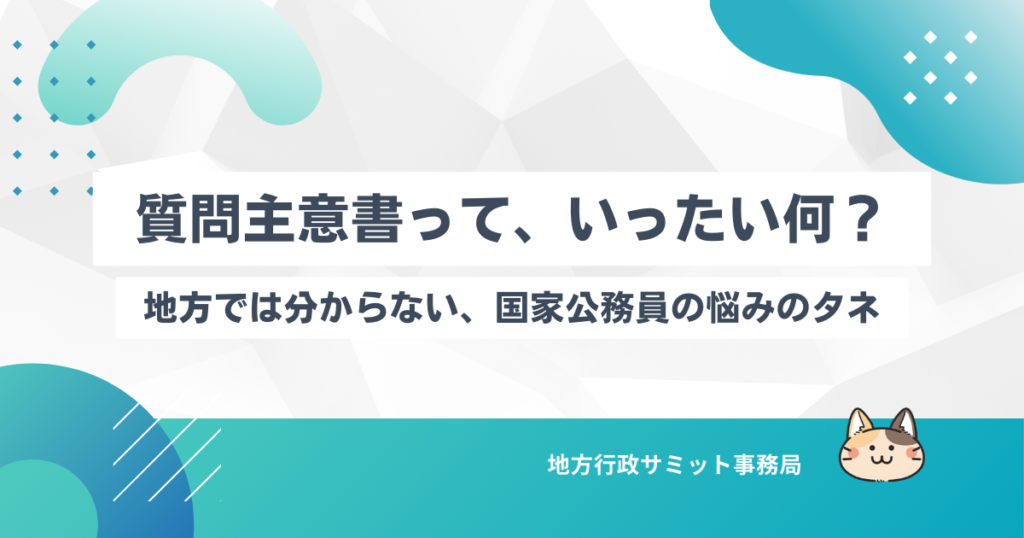
【この記事で分かること】
- そもそも質問主意書とは何か
- 国家公務員は質問主意書のことをどう思っているか
- おもしろ質問主意書とはどのようなものか
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、地方自治体・地方公務員にはなじみの薄い「質問主意書」について、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子質問主意書、国家公務員を悩ませ、困らせる存在なのにゃ…。
そもそも質問主意書とは?
まず最初に、「そもそも質問主意書とは何か?」について、簡単にご説明しようと思います。



質問主意書って、国家公務員にとってはおなじみだけど、地方公務員にはあまり知られていなかったりするのにゃ。
質問主意書の定義
質問主意書とは、日本の国会法第74条〜75条に基づき、国会議員が内閣に対して文書で質問を行う際に用いる公式な文書です。
国会法(抄)
第七十四条 各議院の議員が、内閣に質問しようとするときは、議長の承認を要する。
② 質問は、簡明な主意書を作り、これを議長に提出しなければならない。
③ 議長の承認しなかつた質問について、その議員から異議を申し立てたときは、議長は、討論を用いないで、議院に諮らなければならない。
④ 議長又は議院の承認しなかつた質問について、その議員から要求があつたときは、議長は、その主意書を会議録に掲載する。
第七十五条 議長又は議院の承認した質問については、議長がその主意書を内閣に転送する。
② 内閣は、質問主意書を受け取つた日から七日以内に答弁をしなければならない。その期間内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要する。
この制度は、議員が国政に関する疑問や問題点を内閣に問いただし、その回答を得ることを目的としています。



よくニュースで見る「国の公式見解が閣議決定された」というのは、だいたい「質問主意書に対する答弁書の閣議決定」のことだったりするのにゃ。
質問主意書の提出と処理の流れ
質問主意書については、次のような事務フローを経て答弁書が作成されます。
- 提出:議員が質問主意書を作成し、所属する議院の議長(衆議院議長または参議院議長)に提出します。
- 承認と送付:議長が内容を確認し、承認した質問主意書を内閣に送付します。
- 内閣での対応:内閣は、質問主意書を受領した日から7日以内に文書で回答(答弁書)を作成しなければなりません。この期間には土日や祝日も含まれるため、実質的な作業期間は短くなります。
- 答弁書の作成プロセス:
- 担当省庁の決定:内閣総務官室が質問内容に応じて、各省庁に担当を割り振ります。各省庁は、割り振られた質問に対して異議がある場合、60分以内に申し立てを行い、調整を経て最終的な担当を決定します。
- 答弁案の作成:担当省庁は、割り振り決定後、速やかに答弁案の作成に着手します。この際、他の関連省庁とも連携し、必要な情報や資料の提供を受けながら進めます。
- 審査と修正:作成された答弁案は、各省庁の法令担当課や内閣法制局で、内容の適切性や法令との整合性、用語の正確さなどを確認・修正します。
- 閣議決定:最終的な答弁案は、全閣僚の一致による閣議決定を経て正式な答弁書となります。
- 答弁書の提出:閣議決定後、答弁書は議長に提出され、質問主意書を提出した議員に届けられます。
リストにすると簡単なように見えますが、これらについては、
- 土日祝含めて7日以内に、
- 担当省庁が関係省庁と協議しながら答弁書案を作成し、
- 内閣法制局の審査を経て、
- 最終的に閣議決定を行う
といったように、短期間の間にかなりの作業と調整を余儀なくされることになるため、これが来てしまうと、担当者はかなりの業務量増を強いられてしまいます。


質問主意書の意義と課題
そんな質問主意書ですが、国会議員の立場に立つと、議員が国政の詳細な情報を得るための重要な手段であり、特に委員会での質疑時間が限られる無所属議員や少数会派の議員にとって有効なツールだと言えます。
しかし、各省庁の立場に立つと、短期間でかなりの調整をしながら、適切な答弁書の作成が求められるため、職員には大きな負担がかかります。
特に、質問主意書の提出が予期せぬタイミングで行われると、通常業務に支障をきたすこともあります。そのため、質問主意書の提出や処理に関する制度の見直しや改善は、これまでからもずっと議論の的になっています。
地方公務員をやっていると、質問主意書がないことのありがたみを感じます!
自治体によっては、独自に質問主意書に類似した制度を作っているところもあるらしいですよ。
地方の職員も、自分たちの仕事に密接に関連する国の動きを知るために、たまに質問主意書を見るクセはつけておいた方がいいかもね。
質問主意書の具体的な問題点
さて、そんな質問主意書ですが、具体的な問題点として、どのようなものが考えられるのでしょうか。
官僚への過重な負担
質問主意書は、内閣が受領後7日以内に答弁書を提出することが法律で定められています。
この期間には土日や祝日も含まれるため、実質的な作業時間はもっと限られています。
加えて、答弁書の作成には、各省庁間の調整や内閣法制局での審査、さらに閣議決定など多くのプロセスが必要です。
そのため、関係する官僚たちは通常業務を中断し、深夜や早朝に及ぶ長時間労働を強いられることが少なくありません。このような過重労働は、官僚の疲弊やモチベーションの低下、さらには離職の要因ともなっています。
質問主意書と国会待機は、「霞が関ブラック労働の象徴」といった感じだね。
質問主意書の乱発と質の低下
また、一部の国会議員による質問主意書の多用も問題視されています。
例えば、平成15年(2003年)度には、ある議員が全体の70%以上にあたる3,765ページ分の質問主意書を提出した事例があります。
このような大量の提出は、官僚の負担を増大させるだけでなく、質問の質の低下や、本来の趣旨から逸脱した利用を招く恐れがあります。
結果として、内閣からの答弁も形式的・定型的なものとなり、建設的な議論や政策の改善につながらないケースが増加しています。
具体名は伏せているけど、Wikipediaにも載っている、有名な話だね。
答弁の質と信頼性の低下
質問主意書の増加に伴い、内閣からの答弁の質にも課題が生じています。
例えば、
などとして、「お答えは困難である」と回答を拒否したり、一般論にとどめて明確な回答を避けたりケースが見られます。
このような対応は、国会議員の質問権を軽視するものと受け取られ、政府と国会の信頼関係を損なう可能性があります。また、答弁の質が低下することで、国民に対する説明責任が十分に果たされないという問題も生じます。
制度の硬直性と改善の必要性
現行の質問主意書制度は、提出から回答までの期間が厳格に定められており、柔軟な対応が難しいとされています。
このため、官僚の負担軽減や答弁の質向上の観点から、制度の見直しが求められています。
具体的には、
- 回答期限の延長(7日では答えが整理しきれない)
- 質問主意書の提出に関するルールの明確化(1人何回まで、とか)
- デジタル技術の活用による効率化(質問主意書の一連の事務フローをシステム化する、とか)
といった改善案が考えられるところです。
こういった改善を通じて、質問主意書制度が、本来の目的である政府と議会の建設的な対話の場として機能するようにしていってほしいものです。


おもしろ(?)質問主意書
さて、そんな質問主意書ですが、長きにわたって大量に発出されているものですから、直接担当している職員さんには申し訳ないと思うものの、たまに「なんじゃこりゃ」と思ったり、クスッと笑ったりする質問主意書があったりするのも事実です。
そんな質問主意書の中で、面白かったものを、いくつかご紹介します。
「「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」」質問主意書(鈴木宗男議員)
これは、鈴木宗男議員による、当時の外務大臣・川口順子さんの活動に対して向けた質問主意書です。
「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」が外交に与えた影響に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」が外交に与えた影響に関する質問主意書
一 川口順子元外務大臣が上梓した回想録『涙は女の武器じゃない』(小学館)の二百三頁~二百四頁に、川口氏は平成十四年二月一日に外務大臣に就任し、翌二日にイワノフ・ロシア外務大臣との会談が行われた関係で、
「私はそれまで、日露関係はほとんどタッチしたことがありませんでした。北方四島問題も普通の人間の常識以上のこと、交渉の経緯など、もちろんなにも知りません。会談は昼食会からはじまり、その後部屋を移して会議です。朝十時から二時間勉強会がセットされました。前の晩は記者会見などがあって夜遅くなり、あまり寝ていませんでした。かなり場慣れして度胸がついてきた私でしたが、さすがに不安でした。外務省の人たちはもっと不安だったでしょう。
その朝、せめて着ているものでは少し存在感を出さなければならないと思い、洋服ダンスを開けました。そのとき『これだ』と手に取ったのが赤い服でした。赤い服を着ると高揚感を感じます。」
という記述があることを外務省は承知しているか。
二 当時、外務省は一のイワノフ・ロシア外務大臣との会談に関し、川口順子外務大臣に対して十分なブリーフィング(説明)を行ったと認識しているか。
三 平成十四年二月二日の日露外相会談で、川口順子外務大臣は赤い服を着用したか。
四 三の外相会談で川口順子外務大臣が赤い服を着用し、高揚感を感じたことで、対露関係における日本の国益が増進されたと外務省は認識しているか。
五 『涙は女の武器じゃない』の二百五頁に、
「外務大臣をしているあいだ、『赤い勝負服』といいながら、実は、持っていたのは夏冬一着ずつの二着だけ。そのうちに、九州のある女性が、洋服だけでなく表に見えないところにも赤を身につけていると元気になりますといって赤い××(ナイショ)を送ってくれました。たしかに赤い洋服を二日つづけて着るのもイヤだし、でも国際会議などで「勝負」の日がつづいて気合いを入れたいときもある。そういうときに、この××をひそかに着用したりしていました。」
という記述があることを外務省は承知しているか。
六 「赤い××(ナイショ)」とは具体的に何を指すと外務省は認識しているか。
七 当時、川口順子外務大臣が「赤い××(ナイショ)」を着用して外交交渉に臨んでいた事実を外務省は承知していたか。そのことについて外務省幹部が川口順子外務大臣に対して意見を述べたことがあるか。
八 川口順子外務大臣が「赤い××(ナイショ)」を着用して外交交渉を行ったことで、日本の国益が増進されたと外務省は認識しているか。右質問する。
イワノフ・ロシア外務大臣との会談に向けて、勝負服ともいえる「赤い服」を着た…というエピソードが、川口外務大臣(当時)の著書で語られているのですが、そこには、
「赤い××(ナイショ)」
を着用したという話も書かれています。



文脈からするに、下着のようにも思えてしまうのにゃ…
鈴木宗男議員は、このことについて、質問主意書をぶつけたのです。
そして、こんな質問主意書にも、答弁書はしっかり返ってきます。
平成十八年六月二十二日受領
答弁第三五一号内閣衆質一六四第三五一号
平成十八年六月二十二日内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿衆議院議員鈴木宗男君提出「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」が外交に与えた影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出「赤い勝負服」並びに「赤い××(ナイショ)」が外交に与えた影響に関する質問に対する答弁書
一及び五について
御指摘の記述については、外務省として承知している。
二について御指摘の会談については、外務省として十分に準備を行ったと認識している。
三について外務省として、御指摘の会談において、川口順子外務大臣(当時)は赤い服を着用していたと承知している。
四及び八について外務省として確認することができないため、お答えすることは困難である。
六及び七について外務省として承知していない。
この答弁書では、ざっくり言うと、
- 川口順子外務大臣が赤い服を着ていたことは承知している
- 川口順子外務大臣の著書に「赤い××(ナイショ)」に関して書かれていることは承知している
- ただし、川口順子外務大臣が「赤い××(ナイショ)」を着用していたことは承知していない
というようなことが書かれているわけです。
大臣の着用している服や下着(?)について、真剣に答弁を書かないといけない国家公務員の皆さん…。何ともいえない気持ちになりますね。
まとめ
以上、本日は、地方公務員にはなじみの薄い質問主意書について、ご説明させていただきました。
質問主意書は、国会議員が内閣に対して文書で質問を行い、その回答を得る重要な制度です。特に、少数会派や無所属議員にとっては、政府の見解を問う貴重な手段となっています。しかし、近年では提出件数の増加や一部議員による乱発が目立ち、官僚への過重な負担や答弁の質の低下といった問題が顕在化しています。
さらに、短期間で答弁を作成する必要があるため、深夜残業や通常業務の圧迫といった、省庁側の負担も大きく、制度の硬直性が課題となっています。こうした状況を踏まえ、質問主意書の提出ルールの見直しや、業務効率化のためのデジタル化の推進など、制度改革が求められています。
質問主意書制度は、本来の趣旨である政府と国会の健全な対話を促進するために、より実効性のある仕組みへと改善していく必要があるでしょう。