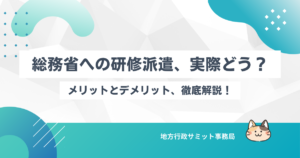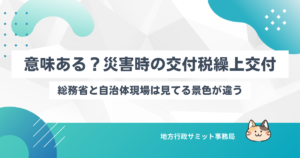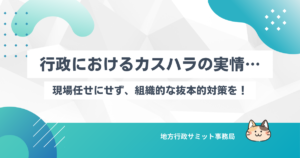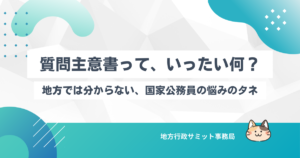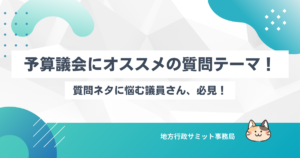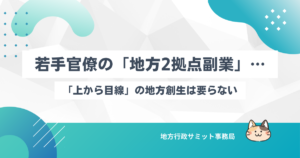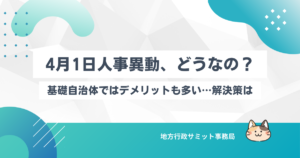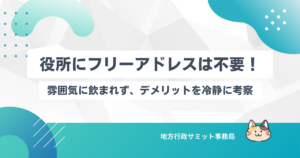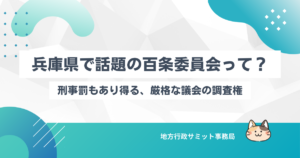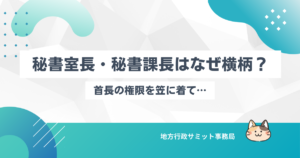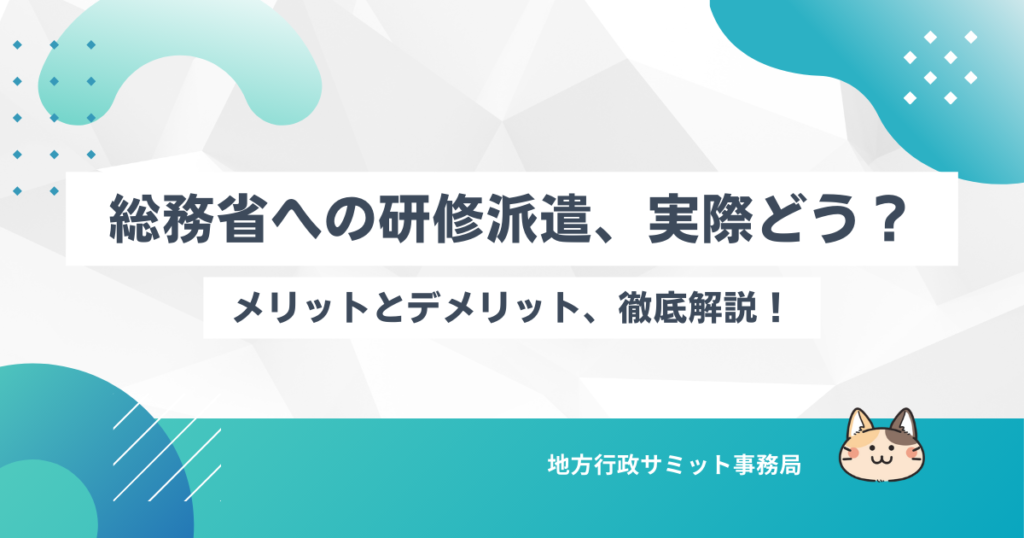
【この記事で分かること】
- 総務省への派遣研修はどのようなものか
- 総務省に研修派遣を送るメリット
- 総務省に研修派遣を送るデメリット
皆さん、お疲れさまです!こちらは、地方行政サミット事務局です!
本日は、総務省への派遣研修について、取り上げて、お話をさせていただこうと思います。
 にゃん子
にゃん子地方自治業界における定番研修なのに、ネット上にほとんど情報がないので、当サイトで徹底解説するにゃ。
総務省との人事交流
総務省では、国と地方の人事交流の一環として、地方公共団体の職員を受け入れています。


受け入れ方としては、いわゆる「割愛」と「研修生」という2つの方式があります。
「割愛」は、復帰を前提にいったん派遣元の地方公共団体を退職し、総務省の職員として採用され、人件費も送付無償が負担する方式。
一方、今回ご紹介する「研修生」は、詳細は後述しますが、ざっくりいうと、派遣元の地方公共団体職員の身分を有したまま、「研修」の位置づけで総務省で働くという方式です。
この総務省への研修派遣制度…正式には「自治実務研修」というのですが、総務省旧自治部局界隈では比較的よく知られた取組ではあるのですが、ネットを探しても、これらに関する情報は、ほとんどヒットしません。
SNSでたまに体験記を語っているアカウントがあるくらいですかね…。
総務省自治実務研修とは
総務省旧自治部局への研修生研修派遣は、「総務省自治実務研修」と呼ばれる形で行われます。
これは、
- 地方公共団体から総務省へ職員を研修生として派遣する
- 研修生は、総務省職員(総務事務官)として基本的に1年間、総務省の職務を行う
- 定期的に研修生向けの合同研修が実施され、総務省幹部職員の話を聞ける
- 人件費は派遣元の地方公共団体が負担する
- 共済組合は派遣元団体のものに加入する
といったスキームで成り立っています。
もう少し具体的に見ていきましょう。
地方公共団体から総務省への研修派遣
この自治実務研修は、地方公共団体から総務省へ職員を研修派遣することによって成り立ちます。
この研修派遣のやりとりは、総務省大臣官房秘書課と、各地方公共団体の人事担当課とで調整し、実現します。
基本的には、どこの自治体も



「総務省へ職員を送って、国の仕事を学ばせたい!」
と思っている一方、受け入れる総務省の方にも約1,700団体(特別地方公共団体を含めばもっと)あるすべての団体から研修生を受け入れることはできませんので、各団体の人事担当課は、いかにして総務省の研修生枠を勝ち取るか、必死で調整にあたっています。


旧自治部局での受け入れが基本
なお、派遣の行先としては、基本的には「旧自治部局」となります。
なので、自治行政局、自治財政局、自治税務局のどこかに配置されることになります。
一般的には自治財政局が特に人気で、それ以外はイマイチ…とされていますが、一方でイマイチのところには人を出さずに派遣先を選り好みしているような団体は、そもそも先述の「研修生枠」が与えられないことも多いようです。
なお、この自治実務研修は、都道府県・指定都市のみならず、一般市も対象となっていますが、その際の調整は都道府県を通さず、直接一般市の人事担当課と総務省大臣官房秘書課とがやりとりをすることになっています。
総務省職員となる研修生
自治実務研修の研修生は、総務省の職員としての辞令が交付されます。辞令には
- 自治実務研修を受けさせること
- 総務事務官に任命すること
が書かれており、これによって、総務省職員としての身分が与えられることになります。
その際の階級は「総務事務官」ということになりますので、ランクでいうと最下位。おおむね、新規採用職員~数年後の職員という位置づけになり、一担当者としての仕事を主に担います。
なお、総務省の場合、担当者レベルのプロパー職員というのは正直あまり多くなく、日々の実務のほとんどを、こうした研修生のほか、割愛と呼ばれる地方団体出身職員が担っている実情があります。
なので、
研修生は、総務省の仕事について、かなり深くかかわることができる
のです。


研修生向けの合同研修
先ほど述べたように、研修生は総務省の実働部隊として、かなり深い仕事までかかわることができるのですが、一方で「研修生」という名のとおり、総務省において、研修を受講することにもなります。
この研修は、総務省の局長級や課長級が講師となり、総務省各局・各課の仕事について講義を受けることとなります。
余談ですが、この研修資料について、課長などのオーダーを受けて、受講する研修生が自ら作成している事例もあります。局長・課長講演資料を担当者が作るというのは一般的にはよくある光景ですが、自らが受講者となる研修資料を作るというのは、なかなか面白い話だと思います。
研修生の人件費は派遣元の地方公共団体が負担する
この「自治実務研修」は、あくまで「研修」ですので、位置づけとしては「派遣元団体が、自らの団体の職務として総務省へ派遣し、研修を受けさせている」ということになります。
ですので、その人件費については、総務省ではなく、派遣元の団体が負担することとなっています。
これは、給料はもちろんのこと、各種手当も同様です。
総務省派遣は、得てして超過勤務が膨大になるので、超過勤務手当が多額となりますが、これも派遣元自治体の負担となります。
また、地域手当も東京都特別区の20%が適用されますが、これも派遣元自治体負担です。
また、引っ越しを伴う派遣の場合、引っ越し代でありますとか、東京での住居についても、派遣元自治体が面倒を見たり、本人対応にしたりするのが基本です。
ただし、総務省の公務として行う出張に係る旅費については、総務省の予算で支出されます。
ちなみに、割愛での総務省派遣については、いったん派遣元団体を退職して総務省に採用されることになり、人件費も総務省が負担します。
なので、人事課としてはできるだけ割愛で送りたいのが本音です。
最近は割愛で送ると、総務省で係長に任命されていることもあるみたいだね。



その係長の部下になった地方派遣職員は、何とも複雑な気分だろうけどにゃ…。
自治実務研修のメリット・デメリット
さて、そんな自治実務研修ですが、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか。
なお、以下のメリット・デメリットは、職員個人というよりも、どちらかというと自治体の人事担当課の目線で書いています。


【メリット①】総務省旧自治部局の仕事を直接体験できる
やはり最大のメリットはこれ、
「総務省旧自治部局の仕事を直接体験できる」
これにつきるでしょう。
地方自治体の根幹をなす地方自治法に関連する事務、オールジャパンで取り組む地域活性化に関する事務、地方交付税・地方債をはじめとした地方財政制度に関する事務、地方財政の根幹をなす地方税に関する事務…
こういった地方自治に関する事務に、国家公務員の立場でかかわり、カウンターパートの仕事ぶりを知ることは、非常に学びが大きく、地方団体に帰った後の仕事において、視野が広がることは間違いなしです。
特に、自治財政局調整課における各府省との地財折衝や、自治税務局各課における各府省との税制改正事項に関する調整は、そういった仕事があることすら地方団体の立場では想像が及ばないものであり、地方行財政がいかにして成り立っているかを学ぶ、非常に貴重な機会です。
また、「ブラックボックス」という批判も強い地方財政計画や地方交付税について、そのしくみがどのようになっているかを知ることができる自治財政局財政課や交付税課も、地方自治体にとって魅力的な学びの場です。
特に一般市職員にあっては、間に都道府県の市町村担当課が入る関係上、日々の職務において総務省職員と直接コミュニケーションをとることができず、大きな情報格差が生じることから、この自治実務研修を通じて総務省の実情を知るメリットは、都道府県・指定都市以上に大きいと言えるでしょう。
でも、総務省の官房秘書課は重要なポストを一般市に渡すことはまずないんだよね…。
【メリット②】国とのパイプができる
自治実務研修で総務省職員となって働くと、総務省プロパー職員が同僚や上司となります。
この同僚や上司は、研修期間中は仕事仲間であり、時間外の息抜きの仲間ともなります。食事をともにしたり、時には親睦旅行に行ったりして、仲が深まっていきます。
そして、この総務省プロパー職員との仲、そして絆は、総務省での自治実務研修を終え、地元に帰った後も、非常に役立ちます。
たとえば、公式には聞きにくい話を、かつて一緒に仕事をした仲間にこっそり聞いたり、国への要望に際して間を取り持ってもらったり…。
こういった、
です。
また、特に総合職(旧I種)職員であれば、将来局長~審議官などの幹部となっていたり、あるいは国会議員や他団体の首長となっていたりと、非常に影響力の強い立場にいるケースも多いです。
普通であれば、総務省幹部職員と気軽に話をすることは難しいですが、かつて研修生として一緒に仕事をしていた仲間であれば、連絡もとりやすいもの。



何ならLINEもつながってて「飲みに行きませんか?」くらいのノリで連絡を取ることも出来るのにゃ。
こういった「国とのパイプ」を作ることができるのも、自治実務研修の大きなメリットだと言えるでしょう。
【メリット③】他自治体職員とのネットワークを構築できる
そして、人的ネットワークについては、何も総務省職員に対してだけではありません。
総務省には、多くの自治体職員が、研修生または割愛という立場で出向してきています。
こういった地方出身の職員は、総務省プロパー職員と違い、完全に立場が同じですので、総務省での苦労ややりがいなどといった思いも共有しやすく、総務省におけるかけがえのない仲間となります。
こういった地方仲間とのつながりもまた、大事な人的ネットワークです。
派遣元に復帰したのち、仕事における情報交換先としてはもちろんのこと、近隣自治体からの出向であれば気軽に食事等に行ける仲間になりますし、遠方からの出向であっても、旅行などで訪ねていき、交流を深めることが可能になります。


【デメリット①】自治体の人件費負担で総務省の労働力として使われる
一方で、総務省での自治実務研修にはデメリットもあります。
その中で、人事担当課が一番気にするのが
「自分のところの人件費負担で、総務省の労働力を提供する」
という点。
もちろん、総務省への派遣によって得られるものは非常に多いのですが、一方で、研修派遣とは建前で、実際は本来プロパー職員がやるべき仕事を、自治体職員が、派遣元自治体の人件費負担で行うというのは、見方によっては
「国による労働力搾取」
ともなりかねません。
もちろん、総務省にはそういった点に関する負い目というか、課題意識はありますので、基本的に研修生を出してくれている派遣元自治体には敬意を払っていますし、研修生をきちんとした職務上のパートナーとして、対等に扱ってくれる傾向は強いです。
他府省の研修生は、本当にひどい扱いを受けていると聞きますよ。たとえば…



おっと、やばい話が出そうなので口をふさぐにゃ!
【デメリット②】総務省の過重労働で職員が潰れるリスク
これは総務省に限った話ではありませんが、霞が関の本府省については、国会対応や予算、法令改正などの事務の負担が非常に大きく、労働時間は自治体職員の水準を大きく上回ることになるのが一般的です。
特に税制改正時期の自治税務局各課、地方財政計画策定時の財政課・調整課、単位費用設定や普通交付税算定時期の交付税課は、常軌を逸した労働時間となることで知られており、
「終電で帰れればまだマシで、タクシー帰りは当たり前、何なら泊まり込みも」
という状況に陥ります。
このような労働環境に置かれると、当然派遣職員の健康状況は著しく悪化し、場合によっては倒れてしまうこともあります。
せっかく自治体の人件費負担で総務省へ人を送り出して、潰されて帰ってきてしまうというのは、自治体の人事担当課としては、なんともやるせない気持ちになりますし、何より本人が気の毒です。
個人的には、ぜひ総務省をはじめとする霞が関本府省の労働環境は改善されてほしいと願うのですが、何しろ組織が巨大な上、官邸や国会という巨大な権力を相手に調整しないと解決しない課題も多いので、そう簡単にこの状況は変わりません。
自治体の人事担当課の立場だと、せめて、心身ともに健康で、頑丈な職員を送り出すように心がけるしかないのが実情です。
この問題が解決しないから、どんどん霞が関から優秀な職員がいなくなってしまうんだよ…。
【デメリット③】東京で転職してしまうリスク
これは特に遠方の自治体から総務省へ派遣しているときに起こるリスクなのですが、地方で働いている職員が、東京暮らしを気に入って、
研修派遣期間中に東京で転職活動を行い、東京で就職先を見つけて、研修期間満了とともに派遣元自治体を退職
してしまうパターンがあります。
転職先としては、東京都特別区や東京都といった、いわゆる「同業他社」への転職のほか、民間企業へ転職したり、あるいはベンチャー企業等を興す強者もいたりします。
派遣元自治体としては、地元復帰後の活躍を期待して、いわば「将来への投資」的に自己負担を甘受しているところもあるわけですが、それがこのような形で無駄に終わってしまうのは、痛恨の極みでしょう。
なお、意外に思われるかもしれませんが、霞が関の本府省に転職する事例はあまりないようです。
おそらく、過酷な労働環境を目の当たりにして、勤続する職場としてはイマイチ…と判断されているのではないでしょうか。



霞が関…憧れられているのか嫌われているのか、分からなくなってくるにゃ。
まとめ
以上、本日は、総務省への研修派遣…正式名称「自治実務研修」について、お話をさせていただきました。
総務省への研修派遣は、自治体の未来を担う職員にとって非常に貴重な機会となるうえ、国や他自治体との人的ネットワークを構築できる、非常に魅力的な取組です。
一方で、自治体の人事担当課の立場でみると、人件費が自治体負担となる中で実質的な労働力として使われることや、通常の労務管理をしていれば許されないような異様な労働環境に貴重な職員を送り込むことへの違和感があるのも、率直に言って事実です。
とはいえ、そういった違和感も、研修から戻ってきた職員が、国とのパイプを生かした情報収集に取り組んだり、総務省で学んだ経験を生かした仕事ができたりすれば、おのずと軽減されていくもの。
自治体の人事担当課は、ぜひ前向きに総務省への研修派遣を検討いただくとともに、この研修派遣に選ばれた職員の方におかれましては、苦労や不安も多いかとは思いますが、ぜひ心意気に感じて、積極的に総務省で活躍してきてほしいと願うばかりです。
そして、研修派遣を受け入れている総務省の皆さんにおかれましては、地方自治体が総務省を、そして霞が関をどのように見ているのかを十分に意識して、大事な研修生を、丁寧に育て上げていただきたいと思います。